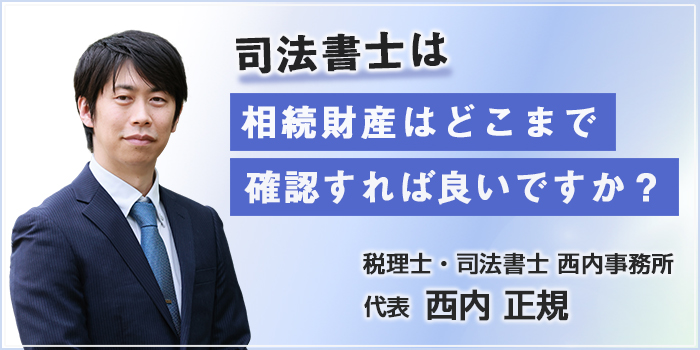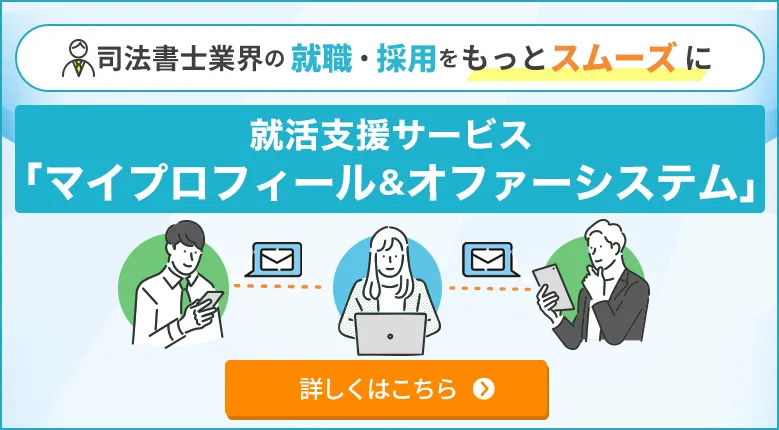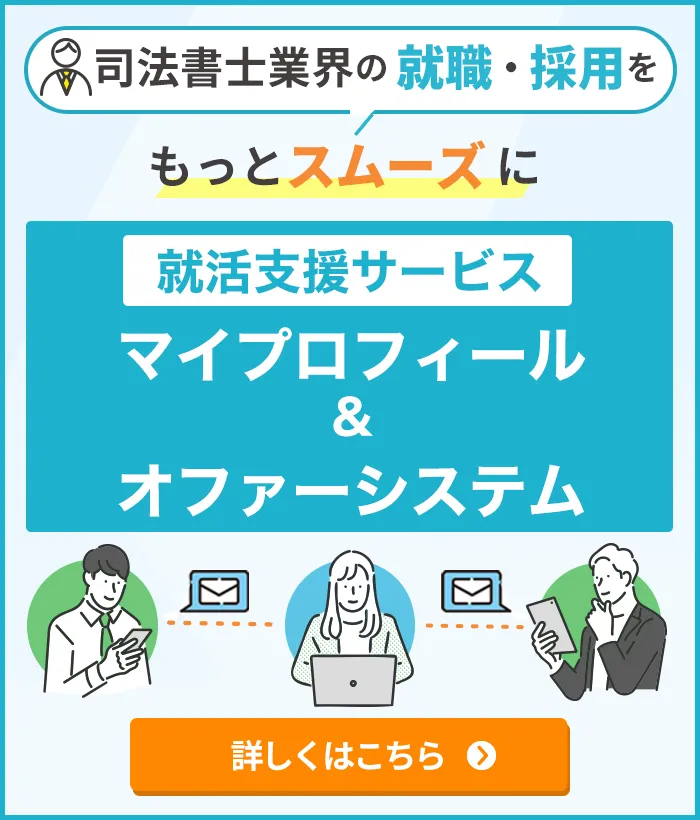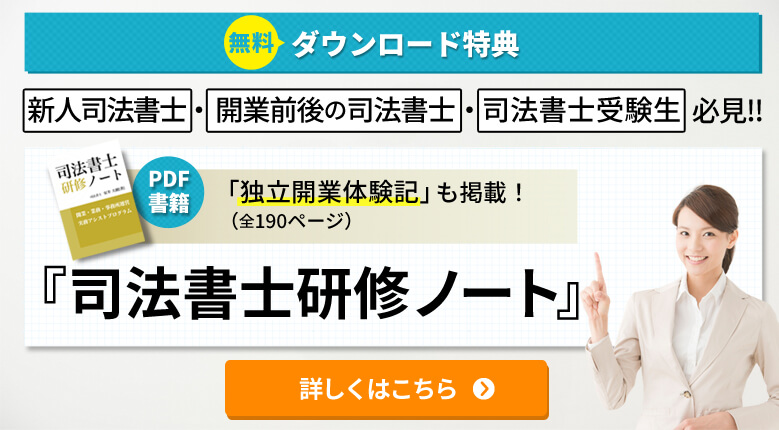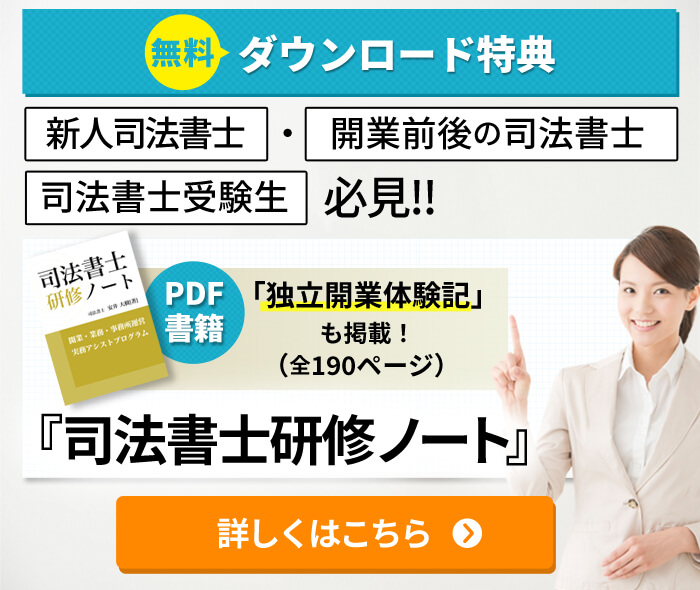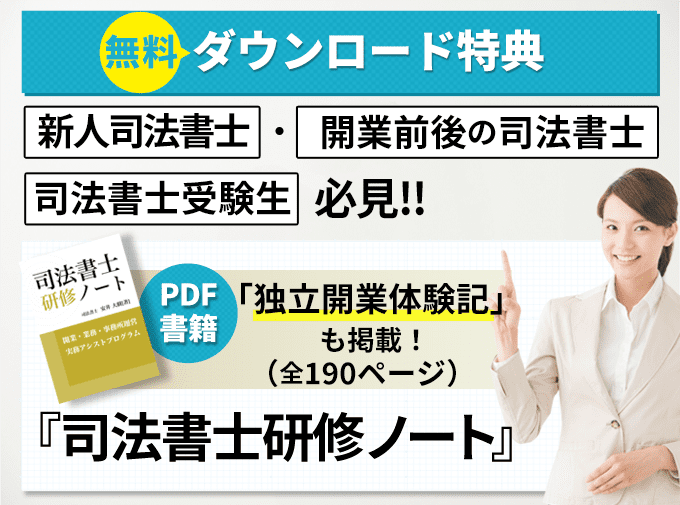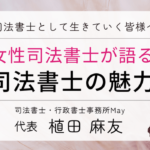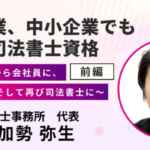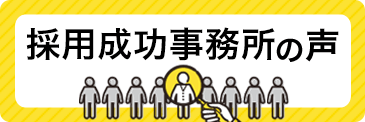目次
ごあいさつ
奈良県生駒市で税理士・司法書士西内事務所の代表をしている税理士と司法書士の西内正規(にしうちまさのり)と申します。
二つの資格を活かした事業をしていると、税務・法務を通じた達観したお客さんへの提案ができる一方、それぞれの知識・経験を深めていく必要性や難しさを日々感じます。
今回、そんな私に「相続財産の確認」をテーマとした執筆の声がかかりました。
税理士としての相続財産の調査方法をお伝えすることで、皆様の司法書士業務でも役に立つのではないかと考え、快諾いたしました。
文字数の限りがあることから細かい補足が及ばない点、各先生方において情報収集していただけますと幸いに存じます。
自己紹介
司法書士試験は令和5年に一発合格しました。
合格当時、大阪国税局の資産課税部門(相続税、贈与税、不動産・株式譲渡所得税を扱う部門)に在籍しており、相続税の調査等を経験していました。
税理士資格はそれ以前に有していたのですが登録はしていませんでした(公務員は資格登録できません)。
二つの資格が揃ったことを契機に独立してみようとの思いが沸き、現在に至ります。
事務所の取扱業務は、資産税申告(相続税、贈与税、不動産・株式譲渡所得税)、生前対策(遺言、後見、民事信託)、不動産登記全般であり、いわゆる相続に関する業務を中心としています。
相続財産確認の必要性
相続財産の確認の目的、内容、報酬について、下表のとおり、司法書士と税理士では大きく異なります。
| 司法書士 | 税理士 | |
|---|---|---|
| 目的 | 相続放棄等の参考に、資産・負債をおおむね把握 | 相続税申告の根拠に、資産・負債を可能な限り正確に把握 |
| 内容 | 負債が大きい可能性があれば、原則3ヶ月以内に相続放棄等の手続きが必要であるため、その把握が必要 | 原則10ヶ月以内に相続税申告が必要でその適正な納税額計算のため、資産・負債とも可能な限り正確な把握が必要 |
| 報酬 | 10万円以内 | 遺産総額の1.0%以内 |
たとえば、司法書士が相続財産を確認する目的の1つに相続放棄の判断資料を提供することがありますが、資産・負債の1つ1つを正確に確認する必要性は低いと思われます。
一方、税理士の目的は相続税申告で適正な納税額計算のため、資産・負債とも可能な限り正確な把握が求められます。
税務当局は膨大な情報を保有しているため、税務調査等で対抗できるよう可能な限り多くの情報を取得しておくことが必要で、有ったことだけでなく、無かったことの確認結果についてもその書類を添付します。
このような資料収集、税法・判例・特例適用要件の当てはめ・判断を行うため、一般的に報酬額が高く設定されます。
資産・負債の確認する内容
代表的なものは下表のとおりです。
資産
| 区分 | 確認する内容 |
|---|---|
| 固定資産 (土地、建物共通) | ・固定資産税の課税明細書 ・固定資産評価証明書 ・名寄帳 ・所得税の確定申告書(税務署への申告書等閲覧請求) ・所有不動産記録証明制度(仮称)R8.2.2~ |
| 土地 | 土地の賃貸借契約がある場合 →各届出書で借地権の帰属、保証金の返還債務の有無を確認 ・土地の無償返還に関する届出書 ・相当の地代の改訂方法に関する届出書 ・借地権者の地位に変更がない旨の申出書 ・借地権の使用貸借に関する確認書 等 |
| 建物 | 居住用、事業用、貸付用を確認し、相続税の小規模宅地等の特例適用有無を判断 ・所得税の確定申告書のうち、青色申告決算書又は収支内訳書 ・通帳、賃料の管理表 |
| 有価証券 | ・証券保管振替機構への開示請求 →該当あれば証券会社に残高証明書を請求 |
| 所在不明株主の株式 | ・株主名簿管理人(信託会社)に照会 ・株式会社のホームページで確認 ・一般社団法人所在不明株主支援機構の検索システムで確認 |
| 取引相場のない株式 (非上場株式) | ・履歴事項全部証明書 ・定款、株主名簿 ・法人税の確定申告書のうち、別表2 等 |
| 単元未満株 | ・会社四季報で株主名簿管理人を確認 →その株主名簿管理人(信託会社)に照会 |
| 預貯金等 | ・通帳、取引残高報告書等 ・最寄りの金融機関・証券会社で利用可能性があるところを整理 →相続時点の残高証明書を請求※農協の様式に注意 ・取引明細証明の請求 ・顧客口座元帳の請求(証券会社の場合) ・伝票や証書の開示請求(ゆうちょのみ) |
| 生命保険等 | ・所得税の確定申告書のうち、控除関係(生命保険や損害保険等)を確認 ・生命保険契約照会制度を利用 |
| 精算金、還付金 | ・後期高齢者医療保険、介護保険等の精算書を確認 ・高額療養費は加入の健康保険組合等に照会 |
| 年金等 | ・最寄りの年金事務所に照会 |
| その他 | ・財産債務調書、国外財産調書の有無を確認 ・貸金庫の有無を確認 →公証人立会いによる開閉を行う |
固定資産
固定資産税の課税明細書はあくまで固定資産税課税のための書類で、少額の場合(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満)には固定資産税を課さない免税点があります。
そもそも保安林や公衆用道路等はこの書類に記載されず、共有物件である場合にはその代表者にこの書類が通知されたり、先代名義の不動産である場合には誰の所有かの慎重な確認が必要です。
これらの理由により財産から漏れてしまうおそれがあるため、固定資産評価証明書や名寄帳を請求することでこれらの確認を行います。
今後、R8.2.2から施行予定の「所有不動産記録証明制度(仮称)」を利用した財産確認が期待されます。
土地、建物
所得税の確定申告書は税務署への申告書等閲覧請求で確認できます。
この請求により税務署に届け出た各種届出書の確認もできます。
土地を貸借し契約書を締結している場合、借地権の帰属や保証金の返還債務の有無、地代や家賃の未収や前受の有無を確認します。
また、相続税の申告上、居住用又は事業用等の建物がある土地は一定の要件を満たすことで小規模宅地等の特例の適用があり一定割合の減額ができます。
青色申告決算書や収支内訳書で賃貸物件の収入金額や減価償却等の欄を確認し貸家や構造物の敷設状況を確認します。
さらに、「借入金利子の内訳(金融機関を除く)」の欄から、金融機関以外の個人間や同族法人からの借入有無を確認できることがあります。
その他の確認書類として、通帳や賃料の管理表があります。
有価証券
証券保管振替機構(以下、ほふり)はH13年に設立され、有価証券の所有権を電子的に管理するもので、証券取引(売買や名義書換)が行われると口座振替の形でスムーズに所有権移転を行います」。
通常、投資家は口座開設時にこの加入申込を行い、ほふりはその加入者情報登録簿を作成します。
この開示請求で口座開設している証券会社等を確認し、その証券会社に残高証明書を請求することで財産の保有状況を確認します。
なお、非上場の投資信託受益権、外国株式、国債、社債等、この対象に含まれないものがあるので注意してください。
所在不明株主の株式
所在不明株主とは株主名簿に記録された住所宛の通知又は催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間余剰金の配当を受領していない者のことです。
株式会社は一定期間公告等することで市場で売却でき、その株主は株主としての権利は失うものの、10年間は売却代金の請求が可能です。
所在不明株主は株主名簿管理人である信託銀行が管理しているため、その信託銀行に照会することで確認します。株主名簿管理人は四季報で確認します。
また、その株式会社のホームページにおいて所在不明株主の氏名等を公表しているため、そこで確認します。
さらに、H27.3に設立された一般社団法人所在不明株主支援機構はこの検索サービスを提供しており、そこでも確認します(要会員登録、有料)。
ただし、すべての株式会社を網羅してしないので注意してください。
単元未満株の有無
上場株式がある場合、単元未満株の有無を確認します。
証券会社の口座でなく信託銀行が管理する特別口座で管理されていることが多く、証券会社の残高証明書だけでは確認が取れません。
株主名簿管理人である信託銀行に照会して確認します。
取引相場のない株式(非上場株式)
非上場会社の創業者やその親族等の取引相場のない株式(非上場株式)の保有状況は、①法務局で取得する履歴事項全部証明書、②その会社が保管している定款や株主名簿、③法人税申告書の別表2等で確認します。
相続税の申告でこの財産評価を行うにあたっては議決権も確認します。
預貯金等
残っている通帳や取引残高報告書等の資料、利用可能性がある近隣金融機関を整理し、照会します。
取引金融機関を確認できれば、相続開始時点の残高証明書を照会します。
金融機関は会社法432条2項に従い取引記録を10年間保管しており、相続税の申告上、生前贈与加算が7年に延長されるため、少なくともこの期間の取引記録の確認が必要となってきます(1年あたり1,080円~6,480円程度の手数料がかかる/金融機関により異なる)。預金取引だけでなく、借入金、出資金(信用金庫、信用組合、農協※の場合)、投資信託等の取引についても確認します。
※農協の場合、「すべての取引を確認したい」旨を伝えて依頼する必要があります。
なお、証券会社の取引記録については顧客口座元帳を請求し確認します。
また、一般の金融機関では伝票等の写しを開示していませんが、ゆうちょ銀行は伝票等の写しを開示請求でき、場合によっては取引を誰が行ったかをその筆跡等で確認します。
取引記録確認におけるポイントは、①その口座の性格(生活用、事業用、投資用、貯蓄用等)、②大口の振込・振替入出金の移動元と移動先(相続人等への贈与、名義資産の有無)、③とくに相続直前の大口ラウンド数字の現金出金(50万や100万円などのATMでの連日出金)、④貸金庫利用の有無等の確認です。
給与・年金・事業・不動産・配当等の収入、保険料・経費・税金・借入返済等の支出がいくらで、年間の可処分所得がどれくらいか計算し、物価や株価等の増減率を考慮することで生前にどの程度の財産を築くことができるかを推計します。
生命保険等
他の財産と同様、相続人からの聴取りから始まり、所得税の確定申告書のうち、控除関係(生命保険や損害保険等)を確認します。
また、生命保険契約照会制度を利用し、一般財団法人生命保険協会に加盟している生命保険会社に照会し、確認します。対象は照会受付日現在、有効に継続している個人保険契約であり、支払済・解約済・失効しているもの等は含まれない点に注意してください。
精算金、還付金
後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、介護保険料の精算は、死亡届が提出されると精算書が送付されます。
また、高額療養費は、加入している健康保険等により異なるため健康保険組合等への確認が必要ですが、一定金額を超える金額が支給されます。
相続後に精算が行われて納付するものは債務、還付されるものは資産です。
年金等
公的年金の未受領等について、近くの年金事務所等で確認します。
その他
場合によって、以下①~③を確認します。
①財産債務調書の有無
所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、総所得金額等の合計額が2,000万円超え、かつ、12/31において3億円以上の財産を有する場合等に財産の種類や価額、債務の金額の必要な事項を記載したものです。
被相続人の財産情報が記載されている重要な資料です。
②国外財産調書の有無
居住者の方で、12/31において5,000万円超えの国外財産を有する場合、国外財産の種類や価額等の必要な事項を記載したものです。
財産は国内のみに存在するとは限らないため、国外財産を把握するのに重要な資料です。
③貸金庫の開閉手続きの必要性
預貯金の取引記録で貸金庫利用の有無を確認します。
貸金庫契約先の金融機関は相続開始の事実を把握した場合、預金と同様に凍結し、原則として相続人全員の立会いがなければ貸金庫を開閉しません。
貸金庫利用がある場合、公証人に立会いを依頼し「事実実験公正証書」を作成する等、証拠保全をします。
負債
| 区分 | 確認する内容 |
|---|---|
| 借入等 | ・信用情報照会制度(CIC、JICC、全国銀行協会)を利用 →各機関の加盟会社との債権債務関係を確認 ※個人間の貸借関係まで確認できない ・所得税の確定申告書のうち、青色申告決算書又は収支内訳書 →「借入金利子の内訳(金融機関を除く)」で個人間や同族法人からの借入有無を確認 ・自宅等を探す |
借入等
信用情報照会制度(CIC、JICC、全国銀行協会)を利用し、債権債務関係を確認します。各信用情報機関に加盟している会社との債権債務関係しか確認できないため、個人間の貸借関係まで確認できない点に注意してください。
なお、上記「資産の土地、建物」の項目でも記載したとおり、所得税の確定申告書のうち、青色申告決算書又は収支内訳書の「借入金利子の内訳(金融機関を除く)」の欄から、金融機関以外の個人間や同族法人からの借入有無を確認できることがあります。
自宅等に契約書や督促状等が残っていないかの確認も必要です。
その他
| 区分 | 確認する内容 |
|---|---|
| その他 | ・相続人の行為能力を確認 ・遺留分放棄の有無を確認 ・遺言書の有無を確認(法務局又は公証役場での検索を含む) ・生前贈与の有無を確認(税務署への相続税法49条の開示請求、申告書等閲覧請求)※贈与税の基礎控除110万円以下の贈与は確認できない |
その他
資産・債務以外では上表の確認もします。たとえば、遺言書について、自筆証書遺言書であれば法務局、公正証書遺言書であれば公証役場での検索を行います。
また、生前贈与について、贈与税申告を提出している場合には税務署への相続税法49条による開示請求や申告書等閲覧請求によりその内容を確認します。
贈与税申告の申告義務が無い、贈与税の基礎控除110万円以下の贈与については確認できないため、相続人への聴取りや通帳・預貯金の取引記録でその有無を確認します。
相続税の申告においては生前贈与加算の対象であったり、遺産分割や遺留分侵害額請求では特別受益に該当するため注意が必要です。
まとめ
今回は一般的な資産・負債の確認する内容を記載しましたが、近年は仮想通貨等のデジタル財産も生まれ、すべての財産を確認することは容易ではありません。
司法書士と税理士では業務内容に違いがありますが、財産調査の限界を知り、どこまでできるのか、どうやって調査をするのかを知る1つのきっかけになればと考えています。
たとえば、相続放棄をするかを判断するには少なくとも負債の確認が必要です。
報酬額によってどこまで労力をかけて確認するかの兼ね合いも当然ありますが、自宅等を探すに留まらず、信用情報照会制度を利用したり、所得税の確定申告書を確認する手段もあります。
先生方の業務の一助となれば幸いです。