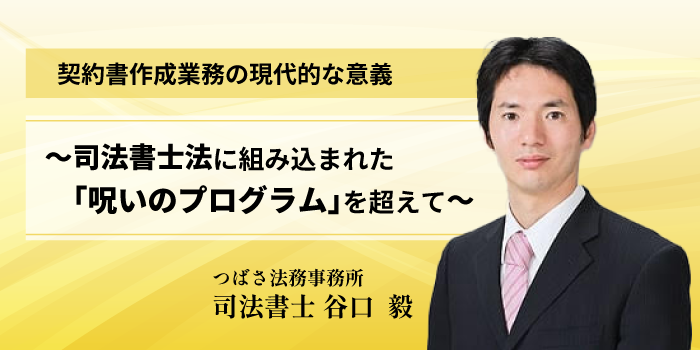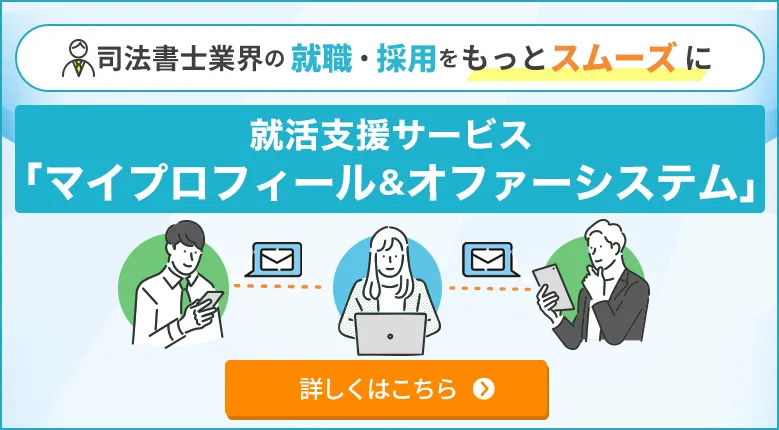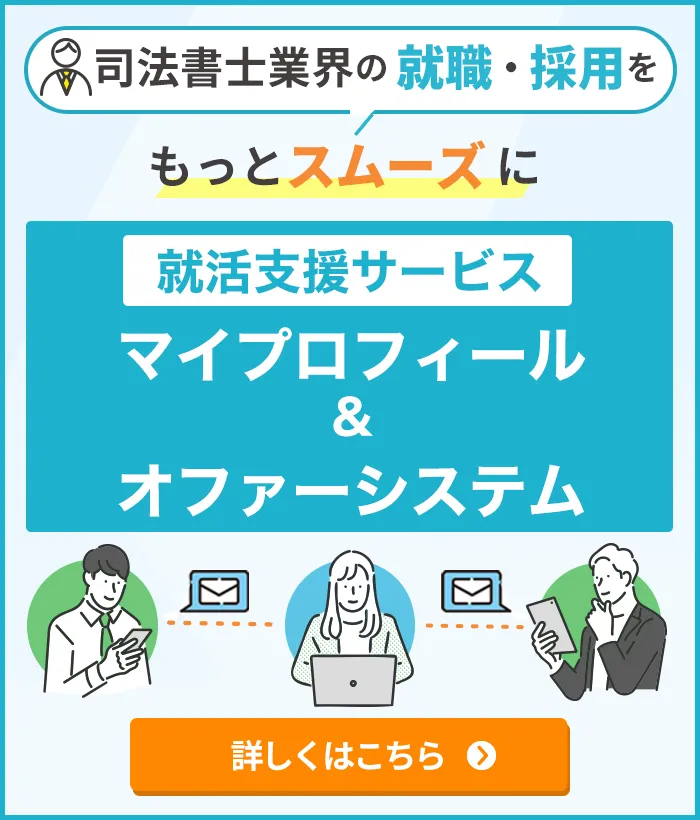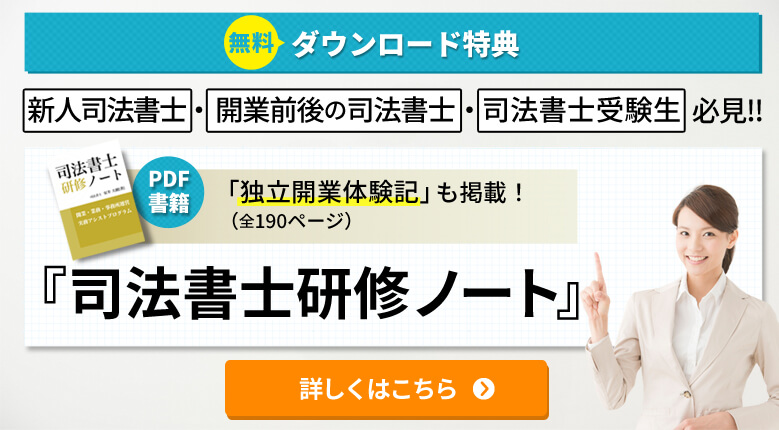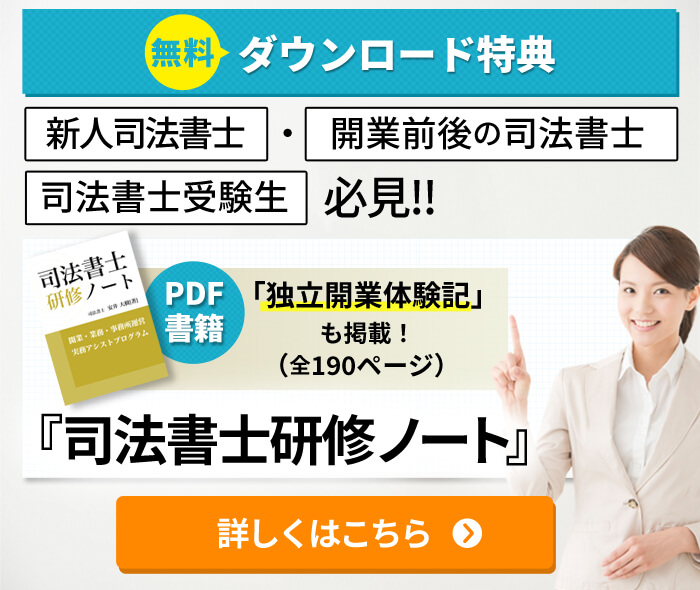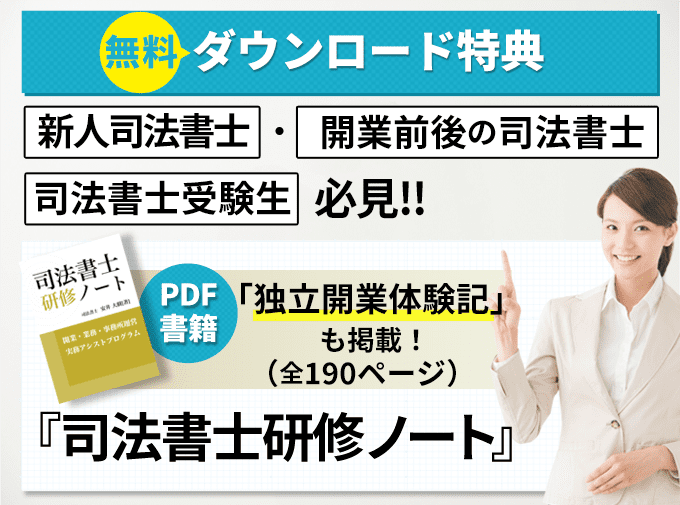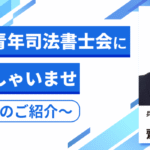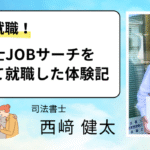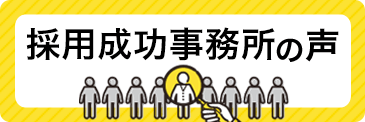目次
司法書士の使命って広い?狭い?
みなさん、令和元年の司法書士法改正で新設された使命規定をしっかり読んでみたことがありますか?よく読むと、摩訶不思議な条文です。
司法書士法に書かれていることしかできないのかな?業務範囲が狭そうだな?という感じがしますね。
次に、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、」です。
法律事務の専門家ってちょっとすごそう。「その他の」がどこまでを指すのかよく分からないけど、色々できそうな気もしてきます。
最後に、「国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」です。
なんか一気に、やらなきゃいけないことが広がりましたね!
一つの条文の中に、「職務範囲狭いよ」「いやもうちょっと広いよ」「実はめちゃくちゃ広いよ」という、矛盾した価値観が綱引きしているんです。
こうしてみると、この短い条文の中に、いろんな力があっちこっちから働いた形跡を読み込むことができるのではないでしょうか。
司法書士の歴史は価値観の綱引きである!
こういう、職務範囲の広さと狭さ、双方の価値観がせめぎ合って綱引きをしてきたのが、司法書士の歴史なんですね!
みなさんも、「◯◯業務って司法書士の仕事なの?その根拠はなに?」っていう議論を、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
この議論、司法書士の歴史上ずーっと繰り返されてきた、価値観の綱引きなんですよ。
遡ってみると、司法書士法の元になったのは大正8年の司法代書人法です。
「自分たちは品位と教養のある在野の法曹だ!それに相応しい法的な位置付けを与えてくれ!」というのが、立法を求めた人々の思いでした。
一方、政府は、「司法代書人なんて教養が要らない文字を書くだけの職業。あれこれ越権行為をできないようにしよう。」と考えて、司法代書人を監督で縛るために法を作ったんです。
価値観の綱引きに負けた状態から制度が始まりました。
司法書士法に埋め込まれた呪いのプログラム
だから、司法代書人法は屈辱的な法律。
業務範囲が裁判所と検事局に提出する書類であると1条で決められたのですが、それを超える仕事をしたら違法であると9条で書かれてしまったんです。
これは、司法書士は代書以外の仕事をしてはいけない、制度が発展してはいけない、という呪いのプログラムを埋め込まれた状態からスタートしたことを意味します。
つまり、司法書士の敵は他士業ではなく司法書士法そのものなんですよ!
司法書士の歴史は、司法書士法に埋め込まれた「発展するな」という呪いのプログラムからの自由を求める歴史です。
市民のための活動がもたらす法解釈の変容
弁護士不在の地域で市民の権利を守っていることも、多重債務への取り組みも、成年後見も、始まった当初は越権行為であり、弁護士法はもとより司法書士法違反と批判される行為でした。
しかし、現場で市民の力となり、知識や倫理を高めて、その時々の社会問題に取り組むことで、事後的に司法書士法の改正に結びつけ、あるいは黙示のうちに司法書士法の解釈の変容をもたらしてきたものです。
現在の我々の業務は、価値観の綱引きの敗北からスタートした司法書士が、綱引きを続ける中で力を蓄えたことで生み出されてきたものです。
批判された行為を追認し、使命とする法改正
こうしてみると、平成14年の法改正の意味が明らかになります。
司法書士法の規定を超える業務をしてはいけない、という「呪いのプログラム」が削除されたのです!
簡裁代理権は、それまで市民のための活動を続けていた実績を認められたうえで付与されました。
さらに規則31条は、司法書士法に規定されていない業務であった財産管理などについて、違法であるという批判を払拭したうえで、正式に追認したことを示しています。
時代に合わせて司法書士の業務が発展してもいいんだ、ということが、ようやく明確になったんですね!
平成14年の法改正で追認された、法3条以外の業務に対して、令和の使命規定ではさらに積極的な意味が与えられます。
法務省の立法担当者が執筆した『注釈司法書士法第4版』の使命規定の解説の中では、「司法書士は、従来よりの主要業務であった登記・供託や訴訟の分野に留まらず、成年後見業務、財産管理業務、民事信託業務等を担う場面も大きく増加しており」と書かれています。
この記述は、もともと違法のおそれがあると言われた法3条以外の業務が、「使命」という次元にまで昇華されたことを示します。
法律関係文書作成の根拠はどこに?
さて。
司法書士は契約書の作成を業務とできるのでしょうか。
民事信託支援業務はどうでしょうか。
その根拠はどこでしょうか。
このような問いを発すると、多くの人は司法書士法の条文を元に答えを見出そうとします。
しかし、「司法書士制度は発展するな」という呪いのプログラムを含んでいた司法書士法に、現代的な業務根拠論の答えが書かれているはずもありません。
私なりの考えは、とりあえずまとまらない形ではありますが、一連のnoteに書きました。
https://note.com/bright_elk319/n/n5e9885cf76f2
ここから始まる52の記事です。
ちょっと雑に書き殴った感じですから、論旨が揺れたりしてますけどね。
さらに、隔月誌「市民と法」第153号(令和7年6月1日発刊)から、
このnoteの内容を大幅に増補・整除して、連載を開始します。
明治から現代までの司法書士の歴史を辿ったうえで、
法律関係文書の根拠を検討するだけでなく、
司法書士という職能が果たしてきた役割や、
司法書士法の解釈がどのように移り変わってきたのか、見てみようと思います!
法律関係文書作成は大正時代からの業務
司法書士は大正時代から現代に至るまで契約書の作成をしていましたが、制度として正面から取り上げられる機会がほとんどないまま、現代に至っています。
業務として理論化してこなかった理由の一つには、司法書士法に組み込まれた「発展するな」という呪いのプログラムの影響もあります。
それ以上に、民間で作成される様々な合意書や契約書などは、わざわざ士業法で独占業務とするほど重要なものとして社会で認識されていなかったと言えるでしょう。
作成できて当然のものでして、別に司法書士制度で中心的に論じるほどのものでもなかったのです。
一方、行政書士法は、契約書作成を独占業務とする趣旨で立法されたものではなく、一般私人を罰するだけの法規範性を有していません。
昭和39年以降、権利義務に関する書面は行政書士の独占業務であるという理屈が行政書士業界の中で編み出されたに過ぎないのです。
そして、司法書士業界に対して、「登記原因証書や定款の作成を含めた添付書面の作成の一切は行政書士の独占業務である」という要求を始めました。
この要求が現代になってマイルドになり、「登記に関係しない契約書は行政書士の独占業務」と変形されてきているのです。
現代は法律関係文書作成業務が重要な時代!
現代に至り、高齢社会になってくると、市民の一人一人が自分らしく生きるために法律を使わないといけない、という複雑な時代になりました。
あなたは認知症になるかもしれないけど、自分の財産をどうしたいの?
認知症になった後にどう生きたいの?
このような問いかけは、今までの歴史上、存在しなかったのではないでしょうか。
契約書作成を正面から業務に据えて、力量と倫理観を高めていかないと、市民の権利擁護ができない時代となっています。
従来の士業の枠組では対応できない時代が来たのです。
司法書士だけでできることなど大したことではありません。
過去の知見が通用しない状況ですから、他士業と力を合わせたり、国や自治体や福祉関係者や金融機関や学者や他士業など、広範な社会のプレイヤーと知恵を出し合い、「自由かつ公正な社会の形成」に寄与するためには何ができるのか、考えていかないといけません。
法律関係文書作成の力量を高めなきゃ!
これは、別に司法書士業界の利益を図る発想でもなんでもありません。
これから先の社会を良くしていくために、私たちに何ができるのか?
私たちに足りない物は何なのか?
こうして考えてみると、今までの士業の歴史で中心に据えられなかった「法律関係文書の作成」というものに、真剣に取り組まないといけない時代がやってきた、といえるのです。
しっかりと論じていきますので、「市民と法」 の連載のご購読も、よろしくお願いします!