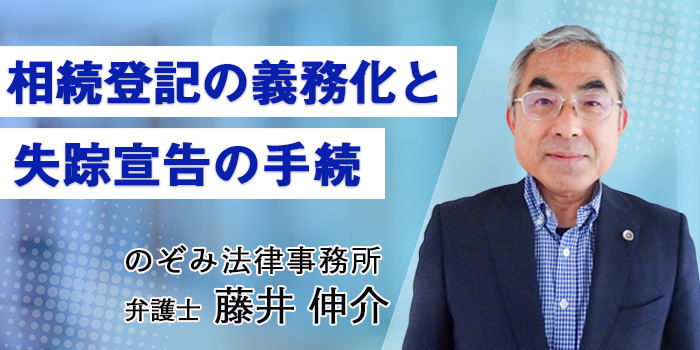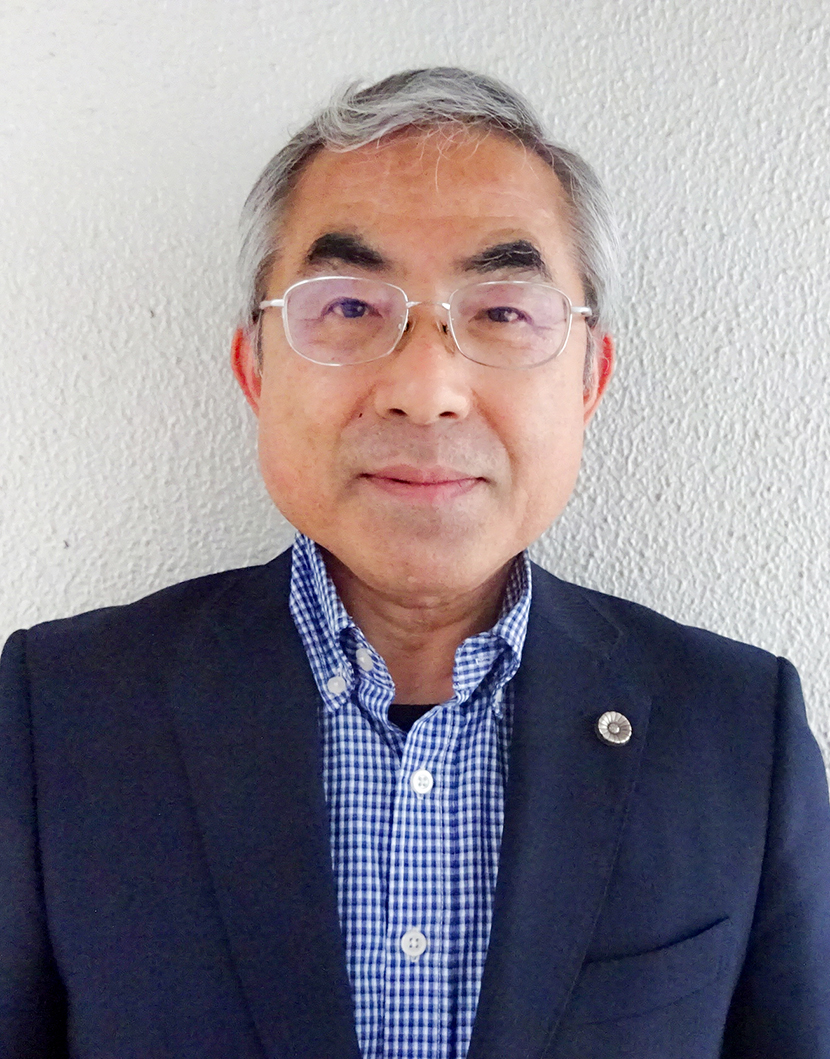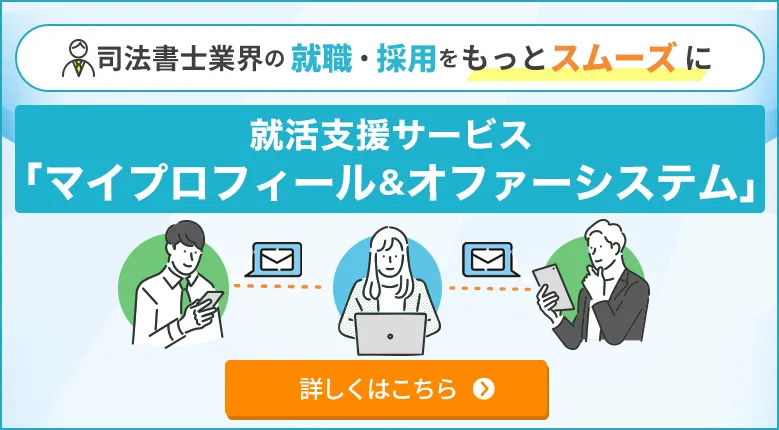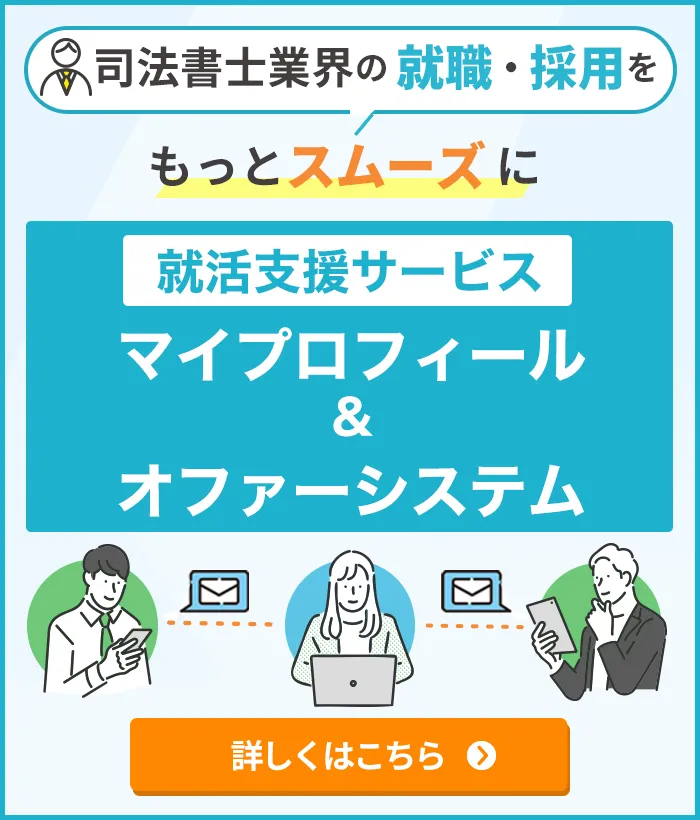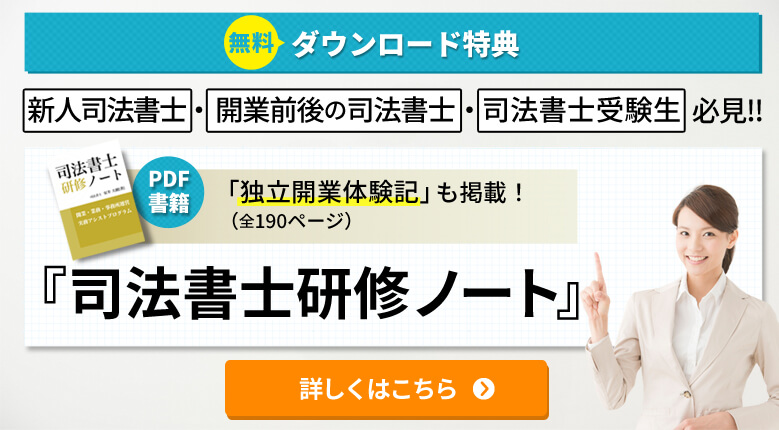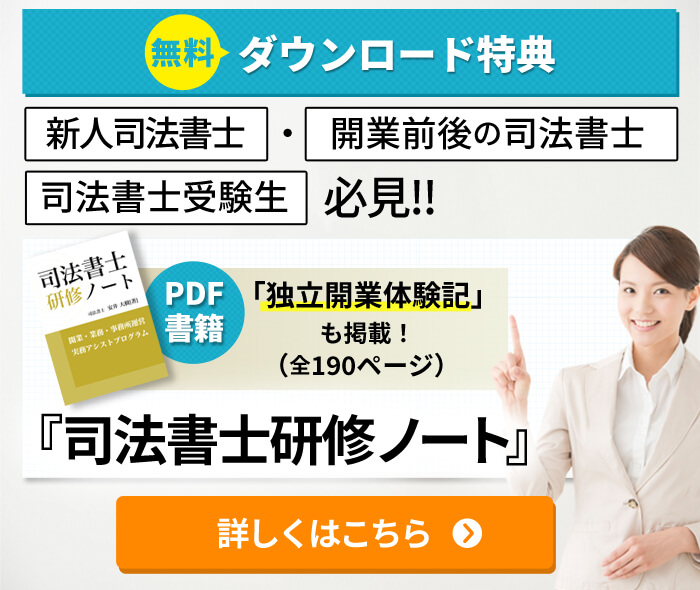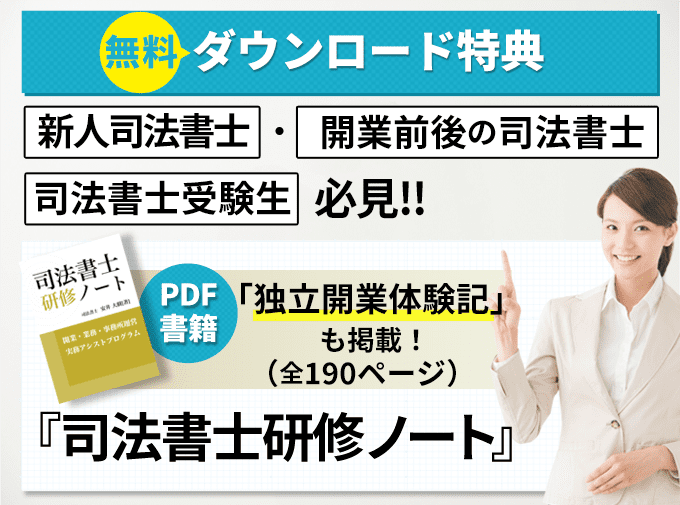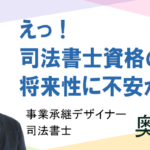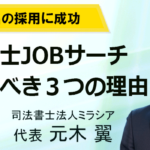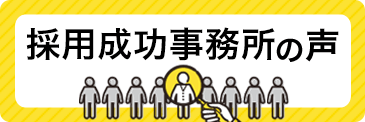はじめに
相続登記義務化が施行された今年4月以降、多くの司法書士は、相続案件に関わることが増えるに違いない。義務化された相続登記を完了するためには、失踪宣告の手続をしなければならない事案も増えると推測している。
空き家特措法の改正法が令和5年12月13日から施行されてはいるが、空き家特措法においても所有者不明土地特措法においても、失踪宣告の申立権限を地方自治体に付与する旨の特例措置は定められていない。
したがって、土地所有者を調査する過程で、登記名義人あるいは相続人資格者について失踪宣告の手続を要する状態であることが判明した場合には、地方自治体としては、所在の判明している親族関係者らに失踪宣告の手続をすることをお願いせざるを得ない。
しかし親族関係者らにとっても失踪宣告の申立は必ずしも容易ではないし、仮に申立をしたとしても、かなりの期間も要する。
したがって、本来ならば、空き家特措法や所有者不明土地特措法の改正作業において、失踪宣告の手続についても特例措置を定めておくべきであった。しかし、法制審議会の改正議論においても、失踪宣告の申立権限については議論されなかったようだ。
以前に私が担当した事案に関連して、失踪宣告の申立権限について、法の不備を指摘して、失踪宣告申立却下決定に対して即時抗告の申立をし、更に抗告棄却決定対して、許可抗告の申立をしたが認められなかった事案を紹介したい。
事案の概要
令和2年8月19日に、知人の社会福祉士からの連絡で、身寄りのないがん患者(以下【幸子様】という。)の相談に乗ってあげてほしいとのことで、同月22日にケアマネージャーにも同席してもらって自宅を訪問し、色々とお話をしたところ、退院して自宅療養を始めたところだが、死期が近いことを自覚しており、身寄りがいないので、色々とアドバイスを頂きたいとのことであった。
そこで、遺言を作成すると共に、死後事務委任契約及び建物管理契約を締結しておき、できれば任意後見契約もしておくのが賢明である旨説明したものの、遺言については幸子様の財産をどのようにしたいのかじっくりと検討することとして、取り急ぎ、死後事務委任契約及び建物管理契約を先行させて、任意後見契約公正証書と遺言公正証書の作成については、後回しにした。遺言公正証書を作成するためにも、戸籍謄本類を取り寄せる必要があった。
再度ケアマネージャーを伴って8月29日に幸子様宅を訪問し、取り敢えず死後事務委任契約書と建物管理契約書に署名押印をしてもらったが、遺言については、その内容についてまだ意向が決まらないとのことであったし、取り敢えずの自筆証書遺言も遺贈先を決定できない状態では書きようがないとのことで、留保せざるを得なかった。
ところが、その翌日に、容態が急変してお亡くなりになってしまった。
幸いにして、建物管理契約書を添付して死亡届を提出したところ受理された。死後事務委任契約を締結していたので、早速葬儀を執り行うこととした。
幸子様は自らを天涯孤独と言っていたが、戸籍を調べると、筆頭者父親欄に死亡の記載がなく、その年齢は、明治43年3月16日生れの110才だった。
厚生労働省が令和2年8月27日に発表した男性の最高齢者(明治43年3月25日生の110才)よりも年上だった。
しかも住所の記載が抹消されて久しい状態であったため、東京家裁に失踪宣告の申立てをしたところ却下された。即時抗告の申立てをしたが同様に却下。
許可抗告の申立てをしたが許可しない決定がなされた。
やむを得ず、110才の父親について管理すべき財産の所在地を管轄する大阪家裁に対して不在者財産管理人選任申立てをして、当職を不在者財産管理人に選任してもらって、不在者財産管理人の資格により失踪宣告の申立てをし、失踪宣告が認められたので、戸籍届出をしたのち、幸子様について相続人不存在の相続財産管理人選任申立をして、当職が相続財産管理人に選任された。
失踪宣告の申立をするためだけに、生存の可能性が絶無の人につき不在者財産管理人選任の申立(無駄な手続)を余儀なくされた訳である。
失踪宣告申立却下審判の要旨
『失踪宣告は、不在者に対し、死亡したとみなされるという重大な結果をもたらすものであるから、「利害関係人」とは、失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有する者をいうと解される。
また、単なる債権者・債務者は、法律上の利害関係を有する「利害関係人」には該当しないと解される。』(中略)『申立人は、不在者との関係において、単なる報酬債権の債権者及び事務処理等を行う債務の債務者であり、不在者の失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有する「利害関係人」に当たらない。』
即時抗告申立ての理由の骨子
1 「不在者」は既に死亡している蓋然性が極めて高く、権利主体(権利能力)たる実質を備えない状態である。にも拘わらず、不在者財産管理人選任の手続を経なければ失踪宣告の手続を開始しないというのは、余りにも迂遠な措置であり、かつ、国家の後見的立場を放棄する態度である。
2 ある不在者について失踪宣告をすること自体について、重大な利害関係を有する者(配偶者や相続人など)が存在しない場合には、上記の如き硬直化した形式的杓子定規な解釈をしていては、「利害関係人が存在せず失踪宣告をなし得ない」という状態に陥る可能性がある。
3 失踪宣告申立のために不在者財産管理人選任申立てをしても、選任された不在者財産管理人が直ちに失踪宣告の申立てをするとは限らない。
不在者財産管理人の職務として失踪宣告の申立てが義務であるとされている訳ではないからである。
場合によっては、選任されてから7年間経過した後に申立てをするという対応をすることもあり得るのであって、不在者財産管理人選任=失踪宣告申立となる訳ではない。
4 「失踪者」が生存していたならば満110歳を超えており、日本における男性の最高齢者よりもさらに高齢であるという本件においては、申立権者に「重大な利害関係」を要求するに足りる実質的な根拠は見当たらない。
5 本件においては、「失踪者名義の財産」は皆無であって、本件失踪宣告申立てが認められて失踪宣告が確定すれば、「失踪者」は、亡岡田幸子の相続開始より遥かに以前に死亡したものとみなすことになるから、「失踪者」について不在者財産管理人を選任して財産管理をさせる必要性は全くない。
6 昨今、空家問題、所有者不明土地問題などがクローズアップされており、それらの問題を解決する際には、「申立権者」の範囲の問題として「利害関係の有無」が議論の対象となることが多いが、本件の如き場合には、不在者財産管理人選任申立てをするに足りる程度の利害関係を有する者には、失踪宣告の申立てを認めても、何ら不都合はない筈である。
即ち、本件における「失踪者」が生存する可能性は絶無であるから『不在者の利益を擁護する』必要性は全くないし、しかも「失踪者の相続人資格者」も存在しないし、遺族も存在しない。
即時抗告却下決定の要旨
原決定は、『不在者の財産管理については、請求権者として利害関係人のほか検察官が規定されている(民法25条1項)のに対し、失踪宣告については請求権者は利害関係人に限られ、検察官は規定されていない(民法30条1項)。
これは、不在者の財産管理は、不在者本人の財産保護のための制度であって、公益的観点から国家の関与が容認されているのに対し、失踪宣告は、不在者について死亡したものとみなし、婚姻を解消させ、相続を開始させるという重大な効力を掃除(ママ)させるものであるところ、遺族が不在者の帰来を待っているのに国家が死亡の効果を強要することは穏当ではないという理由に基づくものである。
そうであれば、民法30条1項の規定する利害関係人については、不在者財産管理人の請求権者におけるそれよりも制限的に解すべきであって、失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有するものと解するのが相当である。』との『制限的解釈』を前提として、本件申立人が有する債権については、法律上の利害関係とは言えないと判断している。
原決定は、『個別の事件における事情に応じて申立て資格を拡張することは、失踪宣告に関する実務の迅速かつ安定的運用を損なうことになるおそれが高いと言わざるを得ない』と判示するに留まらず、本件申立人の『失踪宣告をするためだけに不在者財産管理人選任の申立てをしなければならないとするのは迂遠であり、抗告人に加重な負担を強いるものであり』という主張に対して、『不在者について不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人との間で権利義務の調整を図れば足りる』と判示した。
許可抗告申立理由の骨子
1 本件においては、不在者は既に満110歳を超えており、厚生労働省が把握する日本人男性の最高齢を超えているのであるから、不在者が生存する可能性は絶無であり、そのような生存の可能性がない場合にまで『制限的解釈』をすべき必要性はない。
2 仮に『遺族』を『親族』に読み替えて解釈したとしても、本件不在者について、その帰来を待っている親族など存在しない。戸籍上の親族は生存するが、失踪宣告の手続を進める過程において、その親族に意向調査をすれば、相続権もない親族が失踪者の帰来を待っていることなど、到底考えられないから、その調査をする必要もない。
したがって、本件の如き特殊な事案において、『制限的解釈』をすべき必要性は、見出し得ないと言わねばならない。
3 原決定は、『個別の事件における事情に応じて申立て資格を拡張することは、失踪宣告に関する実務の迅速かつ安定的運用を損なうことになるおそれが高いと言わざるを得ない』と判示するが、申立人について申立て資格を有するか否かの判断は、あらゆる全ての事件について必要不可欠の作業であって、しかも、その判断は、当該具体的事件に即応した個別の判断であって、『法律上の利害関係』の内容に債権債務を有するものを含めたとしても、実務的には、何ら迅速な判断を阻害することにもならないし、実務の安定的な運用を阻害することにもならない。
4 失踪宣告の申立てをするためには、貼用印紙として800円を貼付し、予納郵券として3270円分程度納付すれば足りるが、不在者財産管理人選任申立の場合には、少なくとも30万円、一般的には50万以上の予納金を納付することが求められるのであって、正に桁違いに大きな負担を背負わされることになる。
不在者財産管理人選任申立をせずに失踪宣告を認めれば、僅かの負担で目的を達することができるにも拘わらず、敢えて不在者財産管理人選任申立てをしなければならないとすると、現実問題として、申立てをできないことも十分にあり得る。もちろん、予納金の額よりも少ない債権しか保有しない場合には、諦めざるを得ないこととなろう。
5 民法30条1項の『利害関係人』の意義については、未だ最高裁判所としての解釈基準は示されていない。民法30条1項は、「利害関係人の請求により」と規定しているに過ぎず、具体的にどのような法律関係にある場合に利害関係ありと認めるべきか、何ら例示すらしていない。
もちろん、最高裁判例としてもそのような具体例を示したものは見当たらない。
大審院の判例としては、昭和7年7月26日五民判決(民集11巻1692頁)があるものの、それとても、「民法三十条第一項ニ所謂利害関係人トハ失踪宣告ヲ求ムルニ付法律上正当ノ利害関係ヲ有スル者ヲ指称スヘキコト」と判示しているに過ぎず、いかなる場合に『法律上正当の利害関係を有するか』については、何ら例示すらしていない。
6 【遺族が不在者の帰来を待っているのに国家が死亡の効果を強要することは穏当でない】というのであれば、それは正に、個別具体的な事案において、当該不在者の遺族の存否や当該遺族の意向を調査すべきであって、これらの調査を全くせずに、形式的に申立人資格を【制限的に解釈する】手法は、本来の法解釈の範囲を逸脱するものであって、行き過ぎである。
7 昨今、空家問題、所有者不明土地問題などがクローズアップされており、それらの問題を解決する際には、「申立権者」の範囲の問題として「利害関係の有無」が議論の対象となることが多いが、本件の如き場合には、不在者財産管理人選任申立てをするに足りる程度の利害関係を有する者には、失踪宣告の申立てを認めても、何ら不都合はない筈である。
もっとも、配偶者や推定相続人が存在する場合は、もちろん、それらの『請求権者』の意向を無視することはできない。
しかし、本件における「失踪者」が生存する可能性は絶無であるから『不在者の利益を擁護する』必要性は全くないし、しかも「失踪者の相続人資格者」も存在しないし、遺族も存在しない。
因みに、本件「失踪者」には、本件失踪宣告が確定すれば、失踪者が死亡とみなされる時点での唯一の相続人資格者は亡岡田幸子であった。
したがって、「失踪者の相続人資格者が存在する」などと解すべき余地はない。
8 『不在者管理制度』は、『不在者の財産を維持管理することを本来的な制度趣旨』とするものであるにも拘わらず、当該制度により選任された不在者財産管理人をして、『失踪宣告の申立てをさせる』という取扱いあるいは実務の運用は、不在者財産管理制度の原則的制度趣旨に反するものであって、むしろ背理であるとすら言えよう。
したがって、本来的な制度趣旨からすれば、当該不在者について失踪宣告の申立てをすることは、不在者財産管理人の権限の範囲外であるだけでなく、更に進んで、失踪宣告が確定すれば当該不在者が『権利帰属主体足り得ない』のであるから、不在者財産管理人の選任自体を無効であると考えるべき筋合いである。
失踪宣告が確定すれば、当該不在者財産管理人としての立場の存立基盤が失われる蓋然性極めて高い本件においてまで、不在者財産管理人選任を先行させて、なおかつ、本来的に全く権限外の行為である失踪宣告の申立てをさせるのは、背理である。
許可しない旨の決定の内容
『本件申立の理由によれば、原決定について、家事事件手続法97条2項所定の事項を含むとはみとめられない。』
問題の所在
何が問題か、端的に指摘すると、戸籍上の年齢が110才を超えている場合に、その人物を死亡したと取り扱うために、【失踪宣告】という重厚な手続をしなければならないという法制度自体が、実情にそぐわない不相当な手続を強いることになり、相続人資格者に対して、加重な負担を強いるものであって、相当でないと言わねばならないというのが出発点である。
次に、【民法上も死亡という重大な効果を発生させるためには厳格な手続を経由する必要がある】という点には、それなりの正当性が認め得るとは言えるが、他方において失踪宣告の取消しという制度が認められているのであるから、死亡の蓋然性が極めて高い場合には、取り敢えず音信不通と認められる時点において死亡したものと見做す旨の宣告をしておいて、生存しているとか別の時期に死亡したことの立証をすることにより失踪宣告の取消しをすれば足りる。
しかるに、失踪宣告の申立権限を極めて狭く限定し、かつ、別途不在者財産管理人選任申立を先行させることを強要することは、単に無駄な手続を強要するに留まらず、予納金という過大な負担を背負わせることになる。
市区町村など地方自治体に失踪宣告の申立権限を付与する特別法が制定されれば、かなりの程度負担が軽減されることになるが、現時点においては、空き家特措法についても所有者不明土地特措法についても、改正法が施行されて間もない時期であるから、今後において、当分の間、失踪宣告の申立権限について特例法が制定される可能性は極めて低いと思われる。
そうすると、相続登記の義務化に対応するための努力をする過程において、相続人資格者について失踪宣告申立をせざるを得ない事案を担当することとなる可能性を十分に認識しておく必要があると言えよう。
本書において、敢えて【即時抗告申立書】からの抜粋や【許可抗告申立ての理由】からの抜粋を紹介したのは、【実務家なら誰でもが疑問に感ずる点】についても、裁判所は、木で鼻を括ったような杓子定規な解釈しかしようとしない態度であることを十分に認識し、悲憤慷慨をしたりして無駄な失踪宣告申立をしないよう、【他山の石】として頂きたい、というのが本稿の執筆意図である。