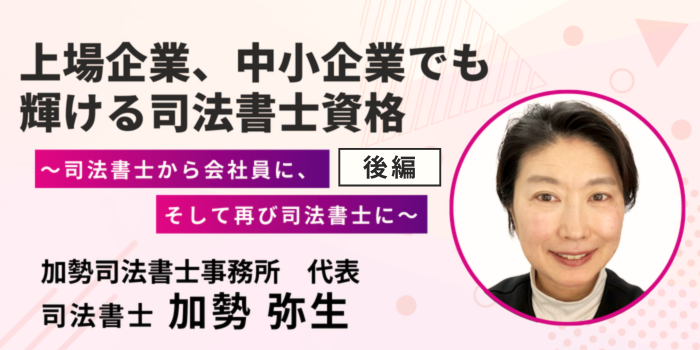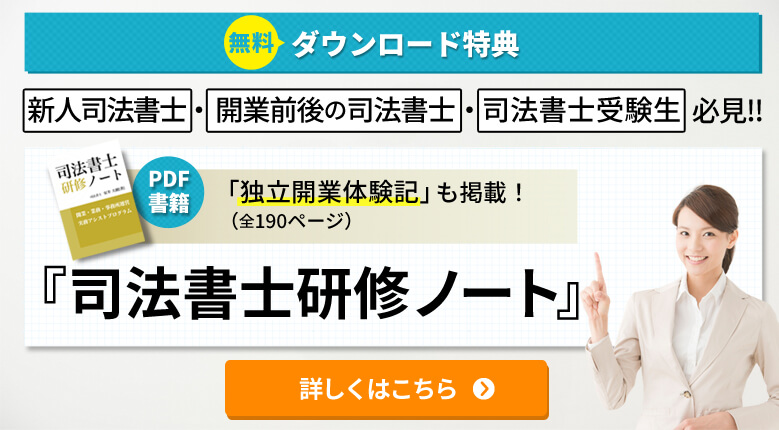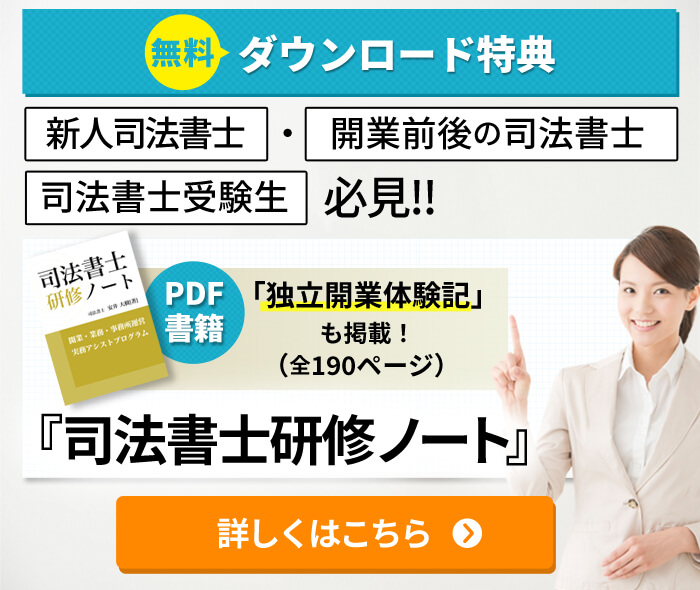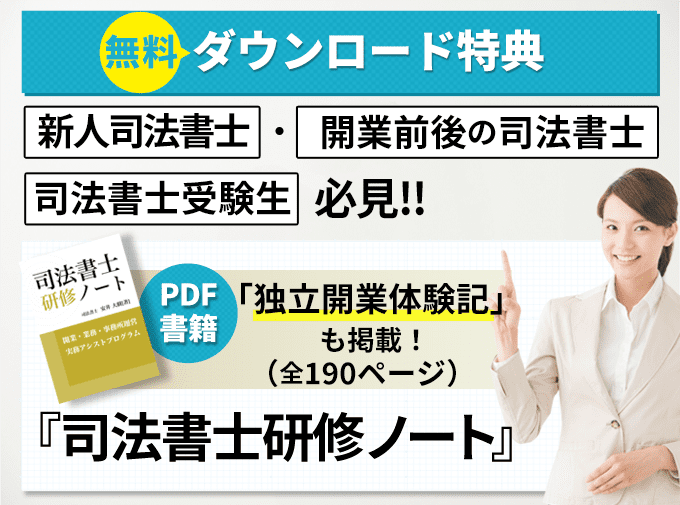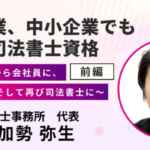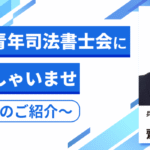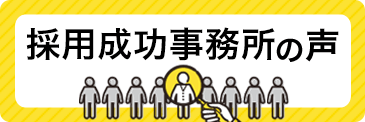司法書士の加勢弥生(かせやよい)です。
前編に引き続き、後編もよろしくお願いします。
目次
事業部門への周知や、日々の関係性構築も重要な仕事
事業部門にリスクの端緒に気付いてもらう
事業部門の法令違反は、特に著名な上場会社では社会的な信用毀損に直結します。
さらに問題なのは従業員個人が犯罪者となってしまうことです。例えばインサイダー取引規制や海外贈収賄規制への抵触が典型例として挙げられ、残念ながら時折関連する報道もされています。
「法令を遵守して事業を遂行しましょう」と言うのは簡単ですが、法務部門が常に全社に目を光らせるのは困難です。法務部門としてできることは、事業に携わる人が自分でリスクの端緒に気が付いて、必要に応じて相談してもらえるようにすること。そのために、まずは法律や制度の周知が必要となります。
B社では、毎年社員向けにコンプライアンス研修を開催していました。そして個人情報保護法や下請法など、日常の事業遂行への影響が大きいものについては個別の説明会を実施。さらに社内の各種研修(管理職研修などの属性別研修)の一部として、その時々のトピックをテーマに話をする時間を設けてもらう、などといった活動をしていました。
反省点としては、本社から遠い拠点ほどこうした啓発が手薄だったことです(特に海外)。以前であれば遠いから・・・という言い訳も(まあまあ)通用していましたが、今はオンラインで研修ができるのでその言い訳も成り立たなくなっています。
なお、こういった研修の一部は自前で実施するほか、外注もしていました。司法書士も外部専門家として、こうした部分をサポートしてあげると喜ばれるかもしれません。
気軽に相談できる雰囲気、関係性をつくる
法務部は、事業部門との関係性構築も重要です。お高くとまっている法務部だと相談しにくく、せっかく何か気づきがあってもそのままになってしまう(そして状況がさらに悪くなる)おそれがあります。
相談依頼があった際には早めにリアクションし、事情をよく聞くことを心がけていました。話を聞いてくれない、決めつけられるといった印象は避けたかったからです。そして、よくよく話を聞いてみると、相談者の考えとは別のところに問題があるケースもありました。
法務部以外の部署も経験
労務部門に異動し、労働法や関連制度にかかわる
B社はグループで9,000人ほどの規模の会社でしたので、組織も様々な部署に分かれています。そして16年も同じ会社にいると、いくつかの部署を異動することになります。
私は法務部の後、労務部という部署に異動しました。就業規則をはじめとした労務関係ルールの立案や運用、雇用条件や福利厚生等の見直し、労働組合対応などを行う部署になります。
そして、この部署でも新法対応を行うことになりました。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」、いわゆる定年後再雇用です。
B社ではほとんどの人が辞めずに定年を迎えます。自身の処遇にかかわることだけに、会社法改正対応時とは比較にならないほどの反応がありました。
そして、このような新法だけでなく、労働基準法をはじめとする基本的な労働法制も一から勉強する必要がありました。何かを学びたいときに会社の費用負担で学習が可能だったのは、今考えるととてもありがたいことです。
労働法制は社員にとって身近な法律なので、頻繁に社内向けのセミナーも行っていました。これもアウトプットの形をとった効果的なインプット方法の一つでした。
このように新しい法律・制度を学び、新しい業務に携わったことで、視野が広がったように感じていました。
その一方で、定年後再雇用制度の設計や労働組合対応を通じ、会社に依存せざるを得ない会社員という立場にやや疑問を感じるようになったのも事実です。
内部監査部門や国際部門も経験
その後、二部署に異動しました。
どちらの部署もリスクマネジメントにかかわる業務でしたが、監査等のため国内外の事業会社への出張の機会が多くありました。海外現地従業員へのヒアリングの機会もあったため、この時期は英語に真剣に取り組んでいました。
余談ですが、海外へのお土産はどの国でもヨックモックのシガールがとても喜ばれます(空港で売っている)。逆にNGなのはおせんべい系です。中でも海苔付きは絶対に避けた方がよいです。
この時期に学んだ「リスクを特定・評価して対応する」(いわゆるリスクベースアプローチ。例:貸金庫で窃盗が発生するリスクを洗い出し、第三者やITによる牽制をすることで対応)という考え方は物事の進め方や対処にも役に立っています。
また、「不正のトライアングル」という概念、すなわち不正の「動機」「機会」「正当化できる環境」の3つが揃うと不正が起こりやすい、という考え方も知りました。司法書士としても、業務遂行や事務所の運営上知っておくと役に立つ概念だと思います。
会社での働き方の特徴
多くの人を巻き込み、協力しながら業務を進める必要がある
会社では一つのプロジェクトに関係する部署や人が多くなります。部署同士で利益が相反することもあり、関係者が納得した上で協力してもらわなければ物事を進められません。
相手は何を重要視しているのか?何が受け入れられて何が不満なのか?を察しつつ対応する必要があります。決して押し付けることなく、方針や必要性をしっかり理解してもらうように、またできるだけ相手の立場を考慮して話をするように努めていました。
ただ、私の上司からの説得であれば納得した人、社長が見学に来たら突然しゃきっと仕事をし始めた人など、人が多ければ多いほどモチベーションもさまざまで、結構苦慮しました。
一方で、全ての人の意見を受け入れるのは不可能です。もし反論があっても対処できるような、しっかりとした方針と理屈を準備するのも重要ですし、そうするようにしていました。
上場会社ならではの慎重さが求められる
上場会社は開示・説明責任があるがゆえに、物事は比較的慎重に進められていました。特にB社では意思決定がとにかく慎重でした。
例えば月1回開催の取締役会は、正式に議案を提出するまでの事務局等との準備期間を含めると、決議まで2か月ほどかかる場合もありました。
会社法によればそこまで時間はかからないはずです。
しかし、全社からの取締役会付議内容の収集、社内での事前検討、社外役員への事前説明等々を経る結果、このようなスケジュールとなっていたのです。
取締役会については特に、出席状況や発言内容、保有スキルなど、役員の活動と能力、そして責任が重要視されるようになったという背景もあろうかと思います。
私自身の仕事を振り返っても、取締役会の付議が必須な案件(新法対応の他、株式分割、自社株取得・消却、投資単位引き下げなど)はとにかくこの「取締役会決議までの期間」を考慮したスケジュール作成がマストでした。
司法書士としても(過度に忖度する必要はないですが)、お客様である会社の意思決定が必要なときに「すぐに決議可能な会社ばかりではない」ことは心に留めておいてもよいでしょう。
札幌にUターンし、また転職
そしてコロナ禍の時代が到来。リモートワークをしつつ、また上司からのリモート飲み会の誘いを断りつつ、今後について考えました。
この時点では東京にいましたが、もともとは北海道出身。いつか戻りたいと考えていたため、思い切ってB社を退職し、札幌に戻ってきました。
札幌でも2社、就業経験があります。いずれも札幌の転職エージェント経由での転職で、中小企業です。総務・法務業務を担当していました。
詳細は割愛しますが、強く感じたことは、やはり法務分野に関しては上場・非上場の差や地域差がある、ということです。
そしてこの差異の部分に、司法書士の商機は間違いなくあると思っています。
一方で、中小企業は組織が小さく社内連携がスムーズであるため、新しい仕組みやITの導入、業務フローの見直し、そして社内の意思決定は迅速に行うことが可能でした。
こうした会社でのプロジェクトのリスクの洗い出しや対応案の提案、進行管理やアドバイスなども司法書士が会社を相手にしてできる仕事の一つではないでしょうか。
また司法書士に戻ったきっかけ
札幌に戻ってしばらくして、同じく北海道に住む私の祖母が亡くなりました。
言うまでもなく相続手続が必要となります。
母が相続人だったので、私が財産や必要な手続を洗い出し、書類を手配。役所や各金融機関の手続に付き添いました。そして遺産分割協議を経て、不動産もあったので相続登記を申請しました。
(元)司法書士としては当たり前の動きでしたが、このとき母が「どうすればいいかわからないときに、わかる人がいるのは心強かった」と言ってくれました。
このように、「何かをやって感謝される」という経験が会社員としては少なかったため(「ちゃんとできて当然」という案件が多い)うれしく感じました。また、こういう知見を必要としている人をサポートしたい、という思いも強くなりました。そして相続だけでなく、これまでの会社員としての経験も司法書士として活用できるのではないか、と思うようになりました。
実務的にも、相続登記を初めてオンラインで申請してみて「昔より少し楽になっているのでは?」と感じたのです(個人の感想です)。
以上のような経緯で、最後に働いていた会社を辞め、特別研修・認定考査を経て、令和6年(2024年)11月に司法書士として札幌で再登録。現在に至ります。
最後に
司法書士とは違った社会経験をしてみるのもよい
私が資格を取った約30年前と違って、士業といえどもいろいろな働き方がある時代になりました。
私のように、司法書士試験に合格したけれども社会人経験がない方、他の分野にも興味があるという方は、年齢にもよりますが会社などで一度司法書士とは違った社会経験をしてみるのもよいと思います。司法書士としては、会社とは通常「登記」という接点しかありませんが、会社に就職した場合は一つ一つの企業活動に深くかかわることができるのも魅力です。
ただし、復職への準備は必要
ただ、多くの方は司法書士になるために受験されていると思いますので、いずれは司法書士に戻りたい、ということであれば、あまり年齢を重ねないうちに復職を実現したほうがよいでしょう。
私自身、司法書士に戻るのはあと10年ぐらい早くてもよかったかな、と思うこともありますが(現在50代)、今日が一番若い日、と思って頑張るしかありません。
昨今では、司法書士を取り巻く法律、制度、手続そして業容に至るまで、目まぐるしく変わってきています。つまり、ブランクが長いと復職のハードルが高くなります。
司法書士とは別のキャリアを積んでいる段階でも、例えば司法書士事務所で副業させてもらうなど、司法書士実務や関連法律・制度の改正に少しでも触れておくことをおすすめします。
なお、私が加入している「日本組織内司法書士協会」には、司法書士資格を持つ会社員や、会社員をしながら司法書士実務に実際に携わっている方もいますので、もし興味があれば入会を検討してみてはいかがでしょうか。