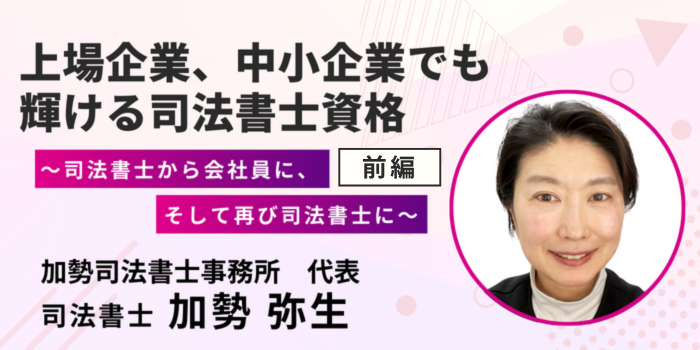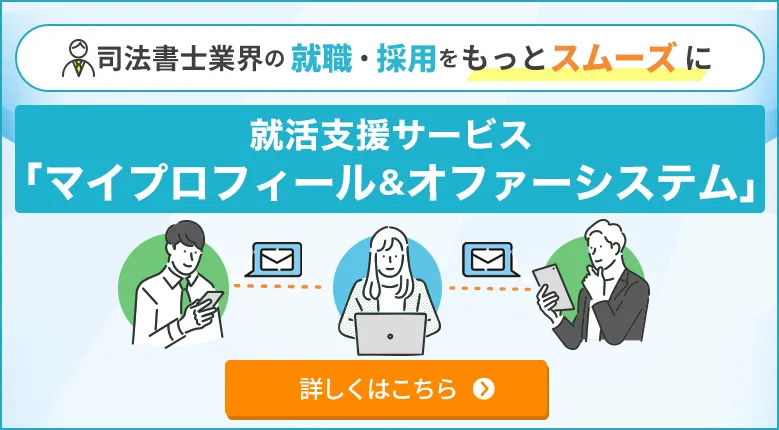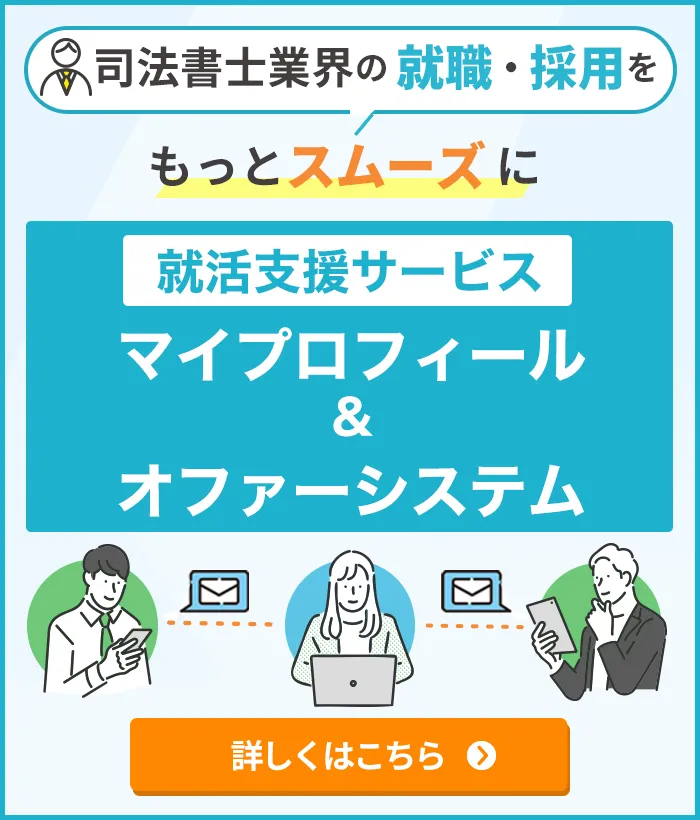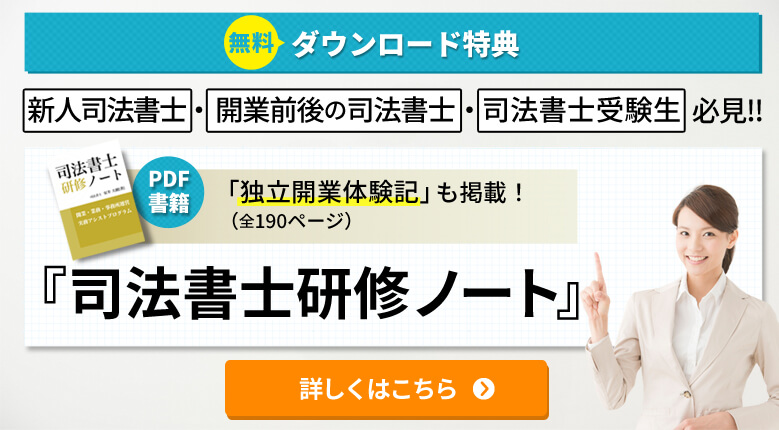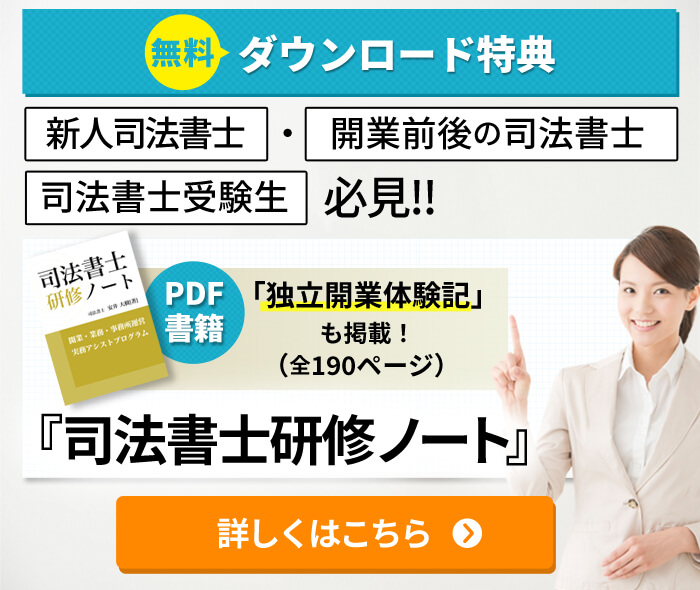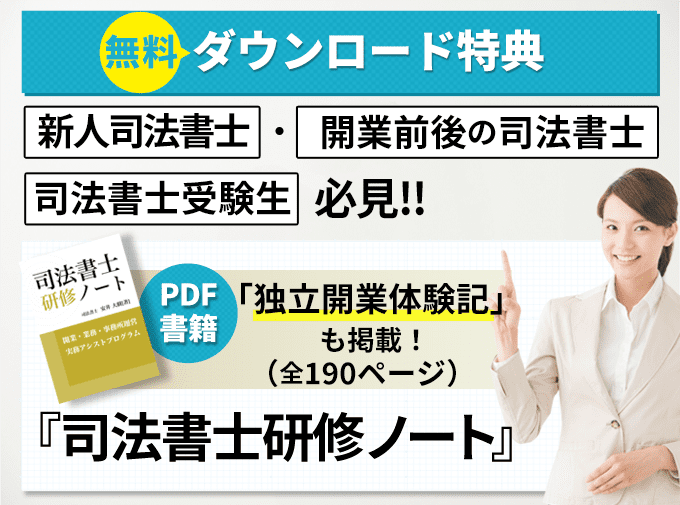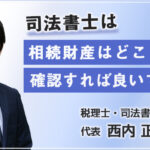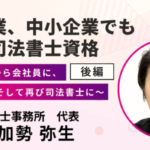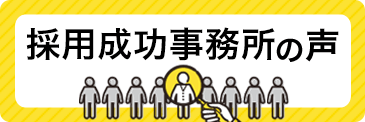はじめまして。司法書士の加勢弥生(かせやよい)と申します。
平成8年(1996年)に司法書士試験に合格しました。今から30年近くも前のことになります。
試験合格後、東京で2年間ほど司法書士事務所に勤務した後、一般企業に転職しました。その後、上場企業や中小企業など環境を変えながら、通算で20年以上会社員人生を送りました。
そして現在、札幌で司法書士として再登録し、開業しています。
このコラムでは、私が司法書士から会社員になったきっかけや転職の方法、会社での仕事内容、そして再び司法書士に戻った理由について書かせていただいています。
司法書士から会社員となったきっかけ
司法書士時代の漠然とした不安
平成8年、私が合格した頃は世の中にも私自身にも「司法書士資格を持ちながら会社で働く」という選択肢はありませんでした。ちなみに、その当時の司法書士登録申請書類では「いずれの組織にも属していない」ことが求められていました。
私も司法書士登録を済ませ、司法書士として受験で得た知識を実地で活かしながら、充実した日々を送っていました。
一方で、大学卒業後の社会人スタートがいきなり司法書士だったため、「世の中のことを何も知らないのに、先生と呼ばれていいのか?」という疑問や不安を感じていました。
特に法人のお客様については内情を知る機会がなく、相手の意図を汲み取るというより、表面上の手続対応に終始していたように思います。
事務所のお客様よりお声がかかる
そんな中、時代は多くのITベンチャーが上場を目指す、いわゆる「ITバブル」を迎えました。東証に新興企業向けのマザーズ市場(現グロース市場)ができたのもこの頃です(平成11(1999)年)。
上場を目指すからには管理部門の充実が必要です。でも人手が足りない。そんなITベンチャー(以下A社)が私の事務所のお客様の中にもいたのです。
ある日、そのA社の社長から「当社に来ませんか?」とお誘いをいただきました。
私も前述の思いがあったため、二つ返事で承諾しました。
「会社のことがよくわかったら、また司法書士に戻る」と決意し転職しました。
しかし、結局そこから20年以上、会社員として過ごすことになったのです。
A社では上場準備と上場後の体制整備にかかわる
A社では管理部に所属。資本政策に沿った増資やストックオプションの発行手続、上場に耐えられる社内基盤の整備(例えば諸規程類や機関運営体制などの整備)といった上場準備業務を担当しました。初めてづくしではありましたが、受験中条文丸ごと覚える勢いで勉強した商法(当時。現在の会社法部分)が役に立ちました。
主幹事証券会社や監査法人、信託会社等にも支援していただき、無事東証マザーズ市場(当時)に上場を果たしました。
上場後は、上場会社としての継続的な体制整備が必要になります。
特に多数の外部株主がいるので、株式管理や株主総会運営は上場前よりシビアに行う必要があります。ここでも商法などの知識のベースがあったので、弁護士、監査法人等の専門家や証券代行(株主名簿管理人)などとの確認や意思疎通も比較的スムーズでした。
証券取引法(当時)や証券取引所の上場規則といった、これまで接してこなかった規制も理解する必要がありましたが、ここでも試験勉強で鍛えられた六法や参考書の読解力が役に立ったよう に思います。
契約書・利用規約の作成やレビュー(精査)に取り組む
IT関連の契約・利用規約の作成・レビューを担当
当初大騒ぎして整備した各種体制も、翌年以降の運用は少し落ち着いてきます。
そしてこの頃は、NTTドコモの「iモード」が全盛期。ITベンチャーであるA社も「iモード」関連のサービスを提供していましたが、そのためには秘密保持契約や業務委託契約などの締結が必要です。私も管理部の法務担当として、関連契約の作成やレビュー、そしてサービスの利用規約作成やレビューを担当しました。ここで役立ったのは、やはり試験勉強で学習した民法・商法(当時)等の知識でした。
契約の作成・レビュー業務の際に意識していたこと
契約は合意により成立しますので、「とにかく譲らない」のではなく、どの部分が妥協可能でどの部分が譲れないかを明確にし、前向きに交渉することが重要です。
当時の営業部門・事業部門の担当者は多忙であり、契約書のレビューや交渉を丸投げされそうなことも多々ありました。
しかし、法的な部分はともかく、事業上どこまでならリスクを取れるかを判断できるのはその担当部門。担当者に主体性を持ってもらい、巻き込みつつ対応することをいつも意識していました。
他の会社も見たくなる
転職エージェントに登録し、転職
A社はITベンチャーという企業の性質上、製品や在庫は持っていません。
契約の内容もITサービス提供を内容とするものでしたが、ここで「製造業はどんな感じなのか?」という興味が出てきました。
A社は当時50人ほどの会社であり、もう少し規模が大きい会社も経験したいという希望もありました。
A社はもともとお誘いいただいて入社していたこと、そして人間関係もよい会社でしたのでかなり迷いましたが、思い切って転職エージェントに登録し、複数社の紹介を受けました。
結果、東証一部市場(現プライム市場)上場の食品製造会社(以下B社、グループで9,000人ほどの規模)に転職することになります。
転職エージェント利用の際の注意点
一定規模以上の会社への転職となると、なかなか知人等のツテはなく、このようなエージェントを使うことが多くなります。
特に法務案件は、求人広告やウェブサイトで掲載されていない非公開案件が多いのです。
注意したいのは、エージェントにより質的な差が激しいことです。
経験上、人として失礼なレベルの人から、こちらの希望を理解した上で、よりよい条件の会社に紹介してくれるエージェントまでさまざまでした。
就職=成約により会社からエージェントに報酬が支払われることになります。このため、こちらの希望は二の次で、とにかく「採用してくれそうな会社」を紹介されるケースもありました。
求職者側は無料でエージェントを利用できますので、もし利用する際にはできるだけ複数のエージェントを比較することをお勧めします。
B社在職中に現行会社法が施行される
自社とグループ各社約40社の会社法対応
このB社には16年もいたので、様々なことを経験させてもらいました。
入社後配属された法務部では、契約書関連や法務相談、そして上場会社としての株式事務、株主総会関連業務、開示書類作成などに携わりました。
そしてこの法務部在籍時に、現行の会社法の公布(平成17(2005)年)、施行(平成18(2006)年)がありました。
上場会社であるB社自身はもちろん、グループの国内子会社・孫会社まで含めた会社法対応が必要となります。対象は40社ほどあったため、自分一人はおろか、法務部員だけでは対処できません。
そこで、まず法務部でグループ会社の属性にあわせ、機関設計をどうするか、定款をどうするか、必要な決議は何か、任期計算や登記申請等々について対応方針をたて、子会社孫会社の管理部門向けに説明会を開いて一緒に対応する形としました。
その後各社の手続面のフォローや進捗確認を行い、なんとか乗り切りました。
もちろん上場会社であるB社の会社法対応は特に間違いが許されないので緊張感がありました。
しかし、非大会社or大会社で非公開会社であったグループ各社の対応の方が、社数と選択肢が多い分大変だった覚えがあります。また、グループ会社の役員変更や任期計算はグループの人事と直結しているため、関係部門との密な連携も必須でした。
司法書士の受験勉強や実務経験はここでも役立った
新たに施行された会社法は、受験で学習した商法とはかなり内容が変わっていましたが、やはり商法のベースがあるのとないのとでは新法対応へのスピード、理解力にも差が出てくると感じました。
また、大勢を巻き込んだプロジェクトとして対応を推進していく必要がありましたが、法律がわかっていると説明のわかりやすさや説得力も違ったのではないか、と自分では思っています。そして登記事項にも影響したため、司法書士の知識経験がダイレクトに活かせる場面でもありました。
法務部在籍中には、この他にも個人情報保護法の施行や株券電子化などの大きな変化にも直面しました。
このような新制度や新法であったとしても、もともと法律の条文や法的文書になじみがあったことが理解や周知の助けになったように思います。
そして新法・新制度対応はゴールから逆算したスケジュールに沿って着実に業務を遂行することが求められます。この点は、司法書士時代の企業再編案件のスケジューリングや進捗管理とも類似していました。
定時株主総会は一大イベント
「間違えました」は許されない
定時株主総会は毎年必ずやってくる、気の抜けないイベントです。議案や議決権行使等に法的な瑕疵が生じた場合、上場会社ではすぐにやり直します、というわけにもいきません。
したがって間違いや漏れがないよう、部門総出、かつ外部専門家にも依頼して慎重に手続と書面を確認しながら進めることになります。法律改正があるときは特に気を使います。株主総会招集通知(広義)の作成や校了は今思い出しても胃が痛くなる仕事でした。
しかも途中から外国人株主のために英文招集通知を作成することになり、発狂しながら作業していました。
各上場会社には私と同じような総会担当者がおり、情報交換のため「株式懇話会」という組織がありました。ここで定期的に改正情報や総会運営、上程議案情報などを共有していました。また実務で役に立っていたのが、宝印刷やプロネクサスといった専門印刷会社が毎年発行する手引きです。この手引きには招集通知の記載例や改正点などが掲載されており、毎年目を皿のようにして確認していました。
誤字脱字を避けるのももちろん重要です。この点は司法書士なら普通の人よりも得意な部分かと思います。
「人が集まるイベント」の側面もある
株主総会は会社法所定の機関であると同時に、実際に多数の株主が来場するイベントでもあります。受付や会場内外の案内係など、総会スタッフは他部門の人や外部派遣業者に依頼しており、彼らへの説明やマニュアル作成、備品準備といった仕事もありました。また、事業報告のビジュアル化も仕事の一つでした。
このあたりの「イベント」要素は法務部門で道筋をつけて、徐々に総務や広報といった他部門に手放していきました。
そして平成23年(2011年)の東日本大震災後は、株主総会の災害対応も大きなテーマとなりました。災害発生時にいかに有効に議決をとるか、という法的側面の他、安全確保、避難誘導を考慮した総会運営が求められるようになり、これらを意識して準備していました。
後編では「事業部門との関係性」「法務部以外の部署での経験」「会社での働き方の特徴(まとめ)」「司法書士に戻ったきっかけ」などについてお話しする予定です。