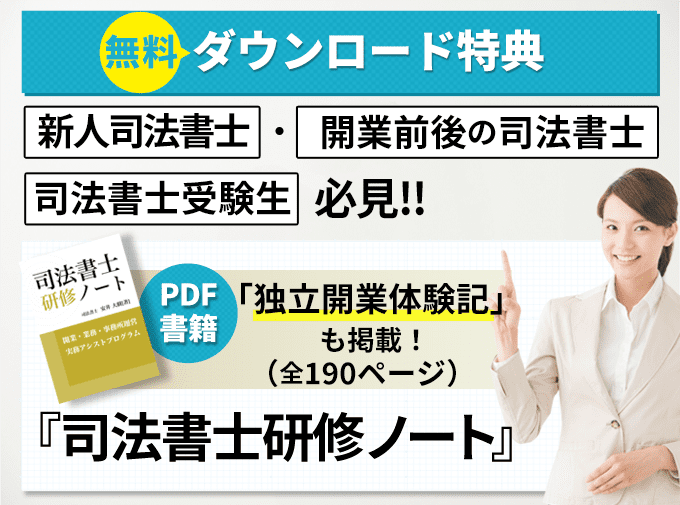不動産登記業務
不動産登記業務は、従前から司法書士の中心業務でした。
今でも不動産登記業務を中心としている事務所は数多くあります。
一概に不動産登記業務中心といっても、事務所によっていろいろな業務形態があります。
デベロッパーや建売業者などの大手不動産会社の指定司法書士であれば、その不動産会社からの紹介による所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記などのある程度定型化した業務を大量にこなしていくことになります。
中小規模の不動産仲介業者から多く依頼を受けている事務所は、それぞれの不動産仲介業者ごとのやり方に合わせて業務を行っています。
金融機関をクライアントに持つ事務所は、融資に伴う抵当権設定登記の手続きや、借り換えに伴う抵当権抹消登記、抵当権設定登記などを行っています。
その他にも葬儀社と提携して相続登記を中心に行っている事務所などもあります。
このように、クライアントによって行う業務も異なってきます。
どのようなクライアントからの依頼でも対応できるよう、知識と技術を磨いておくことが必要です。
また、不動産登記業務は、他士業からの参入障壁が高い業務だと言えます。登記申請の代理業務については弁護士も行うことができますが、実際に登記業務を行っている弁護士は少ないように感じます。
特に不動産登記業務に関しては、抵当権抹消などの簡単な登記以外は司法書士に依頼していることが多いのではないでしょうか。
不動産登記業務の参入障壁が高い理由はいくつか考えられますが、最も大きい理由としては、不動産は一般的に高額であり、登記手続きをミスした場合のリスクが非常に高いということが挙げられます。
本書「3-4-2.損害賠償」の項でも記載しましたが、本人確認や意思確認の過失による損害賠償額が高額になりやすく、これを防ぐためには相応の知識や経験が必要で、生半可な知識や経験ではとても参入できないのです。
参入障壁が高いということは、新人司法書士にとってはある意味でチャンスでもあります。他の業務に関しては、常に他士業との競合ということも意識していかなければなりませんが、不動産登記業務に関しては今のところそのようなことは少ないと言えます。
ただ、そうとはいっても、市場自体が縮小していく中では、司法書士同士の競争が激化していくということを意識し、差別化していくことは必要となります。
不動産登記業務は非常に奥の深い業務です。
調整力も求められますし、不動産に関する知識、税金の知識などの周辺知識や経験が求められることもあります。
新人司法書士のみなさんは、日々研鑽を積んで不動産登記実務に精通するよう心がけましょう。
不動産登記業務でまず抑えておきたいのは、不動産決済業務(立会い)です。
商業登記業務
商業登記業務は不動産登記業務に比べて司法書士の関与率が低いと言われています。
企業の担当者が司法書士に依頼せずに自ら登記を行っているケースもありますが、実際には、本人申請に名を借りて行政書士や税理士が登記申請を行っていることもあります。
これは違法な事であり、司法書士会でも対処しているようですが、現実的にこのような事実があるということは無視できません。
過去には、日本行政書士連合会から法務省に宛てて、商業登記の行政書士への開放の要求がなされましたが、実現しなかったという経緯もあります。
このような事実を考えると、商業登記業務は司法書士間での競争というよりも、まず、他士業との競争と言うことを常に意識しなければなりません。
クライアントに、他士業と比較して司法書士に依頼するメリットが大きいことを感じてもらわなければならないのです。
商業登記においての司法書士の強みは、受験時代から体系的に学んできている商業登記法の知識ですが、ある程度定型化された登記手続ではなかなか他士業との差別化はできません。
一方で、我々司法書士には、会社法、民法、不動産登記法、民事訴訟法などあらゆる法律の知識もあります。
これらの法律知識をフルに使って、企業に発生する問題を総合的に解決や予防できれば、企業にとって手続面だけではなく実体面も相談できる専門家としての価値を提供でき、他士業との差別化ができるのです。いわゆる企業法務です。
商業登記手続きから企業法務へつないでいくという観点が大事なのです。
そのためにも、商業登記手続の相談を受ける際には、まずはクライアントから依頼された登記手続きをそのまま行うのではなく、そもそもなぜその登記を行うのかという実体面の理由や背景を必ず聴き取るようにしましょう。
理由や背景を聴き取ると、クライアントの依頼している手続が、クライアントの経営全体から見て果たして適切なのかという検討もできますし、適切でなければ他の手続を提案することもできます。
聴き取り、会話していく中で、依頼された登記手続以外にも、その企業の抱えている他の課題やその企業の考え方が分かってきて、ポイントを押さえた提案などができるようになってくるのです。
例えば、大きな金額の取引が多い企業であれば、きちんと契約書を交わしているのかどうか、交わしていないならば、将来の紛争の危険性があることを説明して契約書の作成の提案などできます。
クライアントは司法書士が契約書の作成をできることを知らない事も多く、こちらから作成できる事を伝えるだけで依頼をいただけることもあります。
また、それをきっかけに、契約スキームの見直しなどの相談を受けたりと、その企業に深く入り込んで行き、手続きを行うだけの専門家ではなく、企業にとってなくてはならない存在へとなっていくのです。
企業法務
企業法務という言葉は、司法書士の間でよく言われるようになってきましたが、正式な定義はまだありません。
大まかに言えば、企業が事業活動を行う中で発生するあらゆる法律業務をサポートするという業務のことです。
また、その性質ごとに色々な分類ができますが、一般的には、① 臨床法務、② 予防法務、③ 戦略法務に分類されます。
① 臨床法務
紛争が発生した際に、対処し、解決する法務です。
具体的には、訴訟業務、債権回収業務、クレーム対応などがあります。
主に弁護士がその担い手と言えますが、訴額によっては、司法書士が代理人となって債権回収など行える業務もあります。
② 予防法務
将来起こり得る紛争や問題を未然に防ぐ法務です。
具体的には、契約書の作成・リーガルチェック、法律文書の整備などがあります。
予防法務は、司法書士が最も得意な分野と言えます。
訴訟等の出口を見ながら、紛争が起こらないように契約書等の書面を整備していく事は司法書士の知識があればできる事ですし、間違いのない書面を整備することも司法書士の得意とするところです。
また、与信管理において担保の知識なども十分に活かすことができるでしょう。
③ 戦略法務
企業の目的遂行のため、新たな価値を提案し、戦略を立てる法務です。
具体的には組織再編スキームの提案、上場サポート、企業間の不動産取引などがあります。
組織再編におけるスケジュールなどは、登記という出口を理解している司法書士に強みがありますし、企業間の不動産取引においては、決済までの段取りを組んでリードしていくことは、司法書士の専門分野と言ってよいでしょう。
企業法務はまだまだこれからといった分野ですので、新人司法書士のみなさんの努力次第で市場を開拓していけるチャンスが十分にあるといえるでしょう。
財産管理業務
平成14年の司法書士法改正により、司法書士法第29条第1項1号が以下のように規定されました。
司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
(以下省略)
司法書士法第29条は、司法書士法人は定款で定めれば「すべての(個人)司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務」についても行うことができる旨の規定となっています。
そして、これを受け、「すべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務」が司法書士法施行規則第31条に規定されました。
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 (以下省略)
この司法書士法施行規則31条の1号の業務を財産管理業務といいます。
また、司法書士法施行規則31条の業務を、司法書士法第3条に規定する本来的業務に対して「附帯業務」と呼ぶこともあります。
附帯業務については、従前から司法書士も行ってきましたが、明文上の根拠がなく、司法書士業務として当然に行えるとの共通認識はありませんでしたが、司法書士法の改正で明文化されたことにより、これらの業務が行えることに疑義が無くなりました。
財産管理業務の具体例としては、裁判所の選任に基づく相続財産管理人、不在者財産管理人、破産管財人への就任、任意の相続財産管理業務、遺言執行業務、任意売却の代理業務、企業法務、会社や団体の役員への就任、解散会社の清算人就任、法務顧問業務、民事信託業務など幅広い業務が考えられます。
財産管理業務は、最近になって注目されてきた業務で、まだまだこれからといった分野です。
新人司法書士のみなさんにとっても、クライアントのニーズをつかみ、展開していけるチャンスが十分にある分野ですので、積極的に研究してみるとよいでしょう。
裁判業務
司法書士の行う裁判業務として、裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成業務(司法書士法第3条1項4号)があります。
裁判所に提出する書類とは、訴状、答弁書、準備書面、陳述書等の証拠書類などです。
ここでいう裁判所とは、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所で、事件の種類には制限がありませんので、民事事件、行政事件、刑事事件、家事事件、少年事件等全ての事件について、裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。(「注釈司法書士法(第三版)/小林昭彦、河合芳光著」42P)
検察庁に提出する書類とは、告訴状・告発状などです。ここでいう検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁です。(検察庁法1条2項)
司法書士は、これらの書類作成業務を従来から行ってきましたが、平成14年の司法書士法改正により、簡裁訴訟代理権が認められるようになり(司法書士法第3条1項6号)、司法書士の新たな業務となりました。
司法書士に簡易裁判所における代理権が認められた趣旨としては、弁護士の地域的な偏在や、紛争の目的物の価格が少額な場合に弁護士が事件を扱うことは少ないため国民の権利擁護が十分でない状況が生じていたという事実と、一方で、司法書士は地域に偏りなく所在しており、従来から裁判書類作成業務を通じて民事訴訟手続に関わっていたという観点から、司法書士に代理権を付与すべきであると考えられたことによるものでした。
実際に、司法過疎地域など弁護士の少ない地域においては、司法書士に対する民事訴訟等の相談が多いと聞きます。そういった意味では前記趣旨に合致して、司法書士が果たしている本来的な役割は大きいと言えます。
他方、都市部では弁護士数の増加に伴い、簡易裁判所における少額の事件についても弁護士が代理人につくケースが多くなってきている印象があります。
過払事件も減少し、弁護士も増加する中で、司法書士は簡裁代理権をどのように位置づけ、利用していくか、一人一人の司法書士が考えていかなければならないタイミングにきていると言えるでしょう。
司法書士の簡裁代理権の位置づけの一つとして、例えば、登記業務や企業法務など他の業務とリンクしてクライアントの利便性を向上させるという利用方法があります。
普段不動産登記業務の依頼を受けている不動産仲介業者から自社の管理する不動産について賃借人の賃料不払いの相談を受けたり、付き合いのある会社から売掛金回収の相談を受けたりすることがあります。
このような時に、簡裁代理権を利用してその問題を解決していくことができれば、クライアントにとってはワンストップで問題が解決でき、利便性と満足度の向上につながるでしょう。
反対に、新規のクライアントから簡裁代理業務を受任し、その業務を通して信頼関係を構築して、それをきっかけに他業務の依頼を受注するようになることもあるかもしれません。
これは、裁判業務以外にも、他の主要業務を行うことができる司法書士だからこその独自性ということがいえます。
また、全く別の角度から、司法書士の裁判業務に関して大きな動きもあります。近年、司法書士に家事事件に関する代理権を付与しようという動きです。(司法書士法改正大綱:第73回臨時総会にて承認)
もし、将来的に司法書士に家事事件に関する代理権が付与された場合には、更に司法書士の活躍できるフィールドが広がることになるでしょう。
成年後見業務
平成12年4月に成年後見制度が始まって以来、その利用件数は右肩上がりに伸び続けています。
平成28年の成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始、任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で34,249件に及んでいます。(最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況 平成28年1月~12月)
また、親族以外の第三者後見人として最も多く選任されているのが司法書士であり(司法書士9408件、弁護士8048件、社会福祉士3990件)、これは先輩方の努力の賜物であると同時に、今後ますます司法書士の活躍が期待されていると言えるでしょう。
平成28年12月末時点において、成年後見制度(成年後見、保佐、補助、任意後見)の利用者数は合計で20万3551人となっていますがこれは日本の総人口(平成28年10月時点:1億2693万3千人)の約0.16%の割合にすぎません。
国際的なスタンダードとして、最少でも1%が成年後見制度の潜在的利用者である(「成年後見法制の展望 日本評論社/新井誠他」528項)と言われる中で、まだまだ需要を満たしきるには程遠く、今後も件数は右肩上がりに増えていくことが予想されています。
成年後見には法定後見制度、任意後見制度があります。
法定後見制度は、既に判断能力が衰えてしまっている方について裁判所に申し立てをし、成年後見人等を選任してもらうというものです。
類型には、その程度に応じて補助、保佐、後見の区別がありますが、圧倒的に後見類型の利用者が多いのが現状です。
任意後見制度は、本人の判断能力のあるうちに予め契約を締結しておき、判断能力が衰えた時に受ける援助と援助者を決めておく制度であり、任意後見監督人が選任された時から任意後見が発効するという特約を付した委任契約を締結しておくものです。
任意後見は、見守り契約及び財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約など、段階に応じたプランで複数の契約を結んでおくことも可能ですし、遺言との併用も考えられます。この任意後見制度の利用者はまだまだ少ない状況です(平成28年12月末日時点で2461件)ので、今後の活用が期待されます。
尚、成年後見業務に積極的に取り組んでいる司法書士の場合、一般的には、社団法人成年後見センター・リーガルサポートに入会し、その研修を受講し、アドバイスや案件の紹介を受けながら業務を行っているケースが多いのではないかと思います。